文化講座
平三角のポーズ(ウッティタ・パールシュヴァ・コーナ・アーサナ)
ウッテタは「伸びた」
パールシュヴァは「体の側面」という意味です。
コーナは「角度」を表します。
直角三角形にして、体側を引き伸ばすようにします。
方法
- 山のポーズで立つ。
- 両足を6~7足分開く。
- 右足を右に直角に開き、左足先も少し右に回す。
- 息を吸いながら、両腕を肩の高さに上げる。
- 息を吐きながら、右ひざを曲げ、ももとふくらはぎが直角になるようにして、身体を右に倒す。右手は右足の外側の床につける。
- 息を吸いながら、胸を張り出すようにして、左腕を床についた右腕と一直線になるようにする。
- 息を吐きながら、左腕を倒し頭に近づけて、しっかり伸ばす。顔は上向きにして、身体の背面を真っ直ぐに伸ばすようにする。
- 腕、体側、脚が一直線になり、充分に側面を引き伸ばして、3~5呼吸保つ。

効果
大腿二頭筋、殿筋を伸ばし、坐骨神経痛に効果。
特別研修会に学ぶ
H27年8月23日(日)1時から5時まで守山区の白山神社参集所で、京都から先生をお迎えして研修会を開催致しました。ガンガン照りの蒸し暑い日にもかかわらず48名の方が受講されました。
「ヨーガの哲学」と題して「ヨーガ・スートラ」の話をお聞き致しました。
ヨーガとは何かを考えるときに「ヨーガ・スートラ」は、さけてとおれません。
「ヨーガ・スートラ」は古代インドの賢者パタンジャリが編集した、ヨーガの教典です。(パタンジャリは、ヒンズー教の三大神に数えられるヴィシュヌ神の化身ともいわれています)
この教典では、生活全般、生き方にかかわる哲学を、八つの支則として説明しています。
これは「アシュタンガ」とよばれ、これがヨーガとはなにか?という問題に深くかかわってきます。(Asht(アシュト)が八、anga(アンガ)が枝なので「アシュタンガ」はつまり八支則という意味です)
- 禁戒(yama)
- 勧戒(niyama)
- アーサナ(asana)
- 調気法(pranayama)
- 制感(pratyara)
- 凝念(dharana)
- 静慮(dhyna)
- 三昧(samadhi)
ヨーガをする人が守るべき道徳、あるいは頂上にたどりつくまでのみちしるべです。
私たちがヨーガと聞いてイメージするのはポーズの練習ですよね。これは、アーサナという八支則のなかの一つです。
ヨーガは、アーサナ以外にも実践があるということです。
この八つの段階はすべてつながっているということを理解してください。
ゴールには何があるのでしょう?
「ヨーガ・スートラ」を日頃の生活に取り入れ実践していますと、日常生活がヨーガ的になっていきます。日常生活がヨーガ的になった人は、他人に不愉快な感じを与えませんし、ヨーガをすると、みんな姿勢がよくなって、血色も良く、動作もなめらかで、人と衝突しそうになってもスーッと避けられるようになります。
すると健康と幸せになれるのです。
ヨーガのゴールです。
・・・と、先生と言葉の表現は違いますが、私なりにまとめてみました。
アーサナ実習でも一つのポーズへ向かっていくプロセス、ゆったり、言葉少なに、静かな声でのリードから多くを学ばせていただきました。
大変充実した一日でした。
ありがとうございました。

白山神社
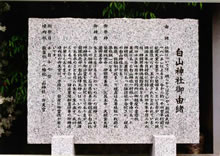
白山神社

講話中

アーサナ指導

アーサナ指導

シャバ・アーサナ リラックス

