文化講座
竹と篠の理美
秋季の竹は、緑々とし高節を有した姿から「平安」の異名として賞愛され、竹の美しい京都を平安京とも称されております。
『万葉集』では、竹と小振りの
一方、篠では「小竹、細竹、四能」の字が充てられ、しなやかさや靡びく姿が詠まれており、その篠を、柿本人麻呂は
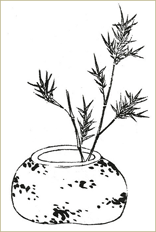
図版[1]
『千筋の麓』
明和5年(1768年)

図版[2]
『生花早満奈飛』
嘉永4年(1851年)
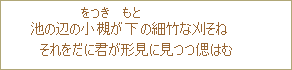
(池の辺りの
その篠竹とおぼしき作品が古書から拾い出せ、
次の歌では、その恋心の深さを竹に託して
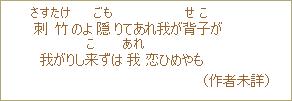
(竹の節間に隠れるように、家に潜んでいて下さい。あなたが私の所に来さえしなければ、こんなに恋に苦しんだりしません)と歌われ、この「刺竹」は、一般的には大宮人や君を指す枕詞ですが、もう一つには節間の長さをして、生長とか茂り栄える意をもつのです。
いけばなの古書から、そんな節間の美しさを象徴的にいけ表わしたものが拾い出せ、六角の黒
そして、竹の清雅な趣きを
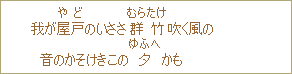
(わが家のわずかな群竹に、吹く風の音が聞こえてくるこの夕暮れであることよ)と、夕風に吹かれてすれあう葉音がうすれていく情景を美しく詠いあげております。
どうぞこの季、竹林を散策しながら、葉のすれあう音に合せて鳥などの鳴声を聴き、清韻さが滞う趣きを感じてみては如何でしょうか。

