雨天の季に入り、樹木などの豊かな林や森を訪れてみると、草木の葉が緑々と繁り、とても美しく観することができます。
この白膠木は、万葉集にて「可頭乃木」と称されており、和歌として、
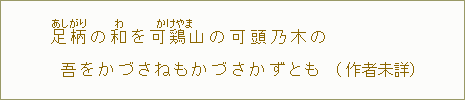 この歌には「譬喩歌」と称され、
この歌には「譬喩歌」と称され、
(足柄の和乎可鶏山の白膠木の木ではないが、私をかどわかしてください。どんなに誘ってもかまいませんから)と詠われております。そして、この歌の「足柄」は、現在の神奈川の足柄山あたりとされ、そして「和乎」は我を指し、「可鶏山」を含める意とすると、私のことを心に掛ける(深く想う)意を表するものとされ、そして、さらに「かづさねも」「かづさかずとも」とは、可頭乃木のかづの同音を重ねられております。そして古来この「かづ」は「勝つ」に通じさせ、ものを得るとか、勝ち取るなど戦勝を意味したものとされ、戦いに赴くときにこの木を餞別とした。それらのことを考え併せると、ここでは「私を早く勝ち得てくださいな」という意味が解けてくる。
この白膠木は、ウルシ科の落葉高木であり、樹腋には漆質があって、物を接合させる性質があるので、男女の強い接合を願った、この歌にふさわしく思えたからであります。その葉の姿形は大形の羽状複葉で、その葉は薬用として「虫瘤(虫卵、虫巣)」から薬用の五倍子を取り得、御歯黒などの染色材料としても古くから用いられております。
そして、さらに別図の『本草図譜』に「ぬるで、かつのき、えんふし」とあり、さらに「
勝軍木、さいはいのき」との異名も記され、その図は、
実時で、葉も紅葉したものが美しく描かれ、これを「ぬるでもみじ」と称されております。
そんな、美しき可頭乃木に青葛藤の花を、古代コスタリカ彩文土器に挿花頂しました。
この緑々とした、夏の季に山里の緑々とした可頭乃木を観して、
白膠木と呼称させて観して下さい。
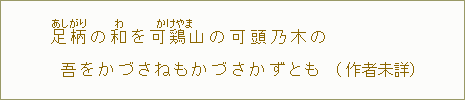 この歌には「
この歌には「


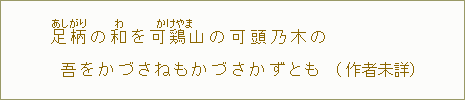 この歌には「
この歌には「
