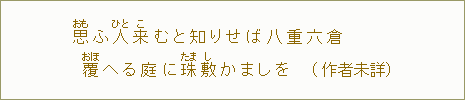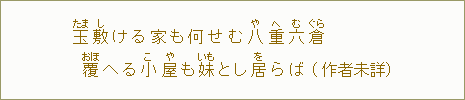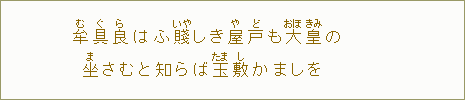夏の季に入り、山野の草木は緑々となりて、丘や野の道端の小道には、葛や金葎などの蔓性の万葉の植物の生ひ繁る姿を、よく観することがあります。
その蔓性の金葎は、葎草の字が当てられ、桑科の一年草で、荒地や野原に生え、茎や葉柄にはこまやかな逆刺があり、五葉の対生する葉には刺毛が生じて、手で触れると僅かな痛みを感じます。
その金葎は、万葉集では四首詠まれております。そのうちの二首は「八重六倉」と称し、作者未詳の「比喩歌」として、
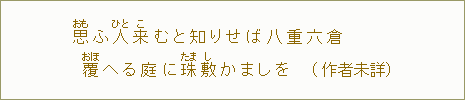
(私の恋しきあなたが、お出で下さると知っていたなら、この金葎が沢山に生い茂って覆われた庭にも、玉を敷き並べて、あなたをお待ちしましたのに)と、幾重にも生い茂った葎の姿から、女性の恋心の重なりの深さが詠ぜられております。
そして、この歌の比喩として、男性の歌で、
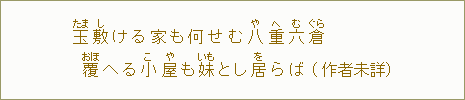
(玉を敷いた家でも私にとって何になりましょう、雑草の如きたわわに生えた金葎に覆われた小屋でも、あなたと一緒におりさえすれば、何も不足はありません)と恋心の深さを、前の歌に答えて切々と詠ぜられております。
そして、さらに次の歌では、橘諸兄が聖武天皇を迎えた折りの歌として、
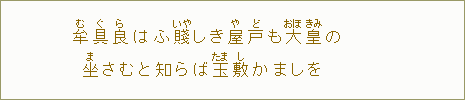
(金葎の延い伸びている姿の如き、卑しいこの私の宿も陛下さまがお出で遊ばすと予め知っていましたなら、玉を敷き並べてお待ちお受けいたしましょうに、まことにむさ苦しい所で恐れ入ります)と詠ぜられております。
この歌が示すように、金葎の延い伸びる姿は、まさしく雑草の如き姿として歌われておりますが、その生命力の高さから後年には「金」の字が当てられて言祝なる文字感が漂って居ります。
 図版[I]
図版[I]
江戸時代の日本の最初の植物図鑑としての『
本草図譜』には「
葎草、かなむぐら、すくもかつら」と銘され、金葎は七月の末から八月にかけて、とても愛らしき小花を咲き
薫いたる図を、図版[I]で参照して見て下さい。そして、さらに別名として「うぐら、もぐら」とも称されております。
 図版[II]
図版[II]
そして、七月の上旬頃に、緑葉の生々しき蔓の延い伸びたる姿の金葎に古き時代の
荒目籠に
河原撫子を添え挿けた挿花を図版[II]で観してみて下さい。
そして、この夏の季、自然の草木の生えたる野や林などから、楓に似ての緑々とした五弁の葉に、細き蔓を延い伸ばした金葎の生命感美を観してみて下さい。