文化講座
蘞の木の理美
初夏から梅雨を迎える季、山里では真白な可愛い花を垂れ咲かせる
『万葉集』では、「
とりわけ梅雨のころには、たわわに咲く花に雨が降り注ぐと、
そんな姿の花を『万葉集』では、「古今
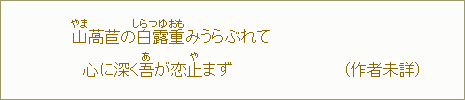
(蘞の木の花が白露の重みで撓わむように、心も深くうちしおれて恋は止むことがないことだ)と、蘞の花の懸け垂れる姿のように、私の恋への思いの深さがまさに同じであると切々と歌い

図版[I]

図版[II]
そして、次の「花に寄せき」と題した歌では、
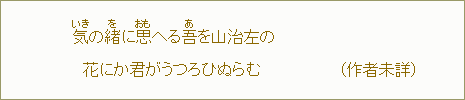
(命をかけて愛している私なのに、蘞の花のようにあなたは心が移ってしまったのであろうか)と、「気=息の緒」命がけで愛しているのに、梅雨の季を迎え、はらはらと白い花弁を止めどもなく散らすが如くの花の姿を、恋人の心が離れていき、正に愛情が衰えてゆくことだと、この歌でも切々と詠じられております。
そんな蘞の木は、晩夏から初秋の頃に卵形の小さな果実を結び、成熟すると果皮が裂けて黒褐色で堅い種子が出、その果皮を
即ち、蘞は「えぐい=えごい」ことから銘せられとされ、別名としても「あかんちゃ、いっさいえご、かきのきだまし、くそざくら」などの名を拾い出すことができます。
その果実と花の図、そして「ちしやのき、えごのき、ろくろき」の名が記された、江戸時代の『本草図譜』の図版を[II]で参照して見て下さい。
この初夏から梅雨の季には、是非とも蘞の木に出合って白く懸け垂れ咲く花姿に、また散る姿に合せて、大地の真白で可愛い花

