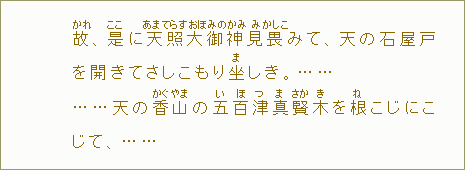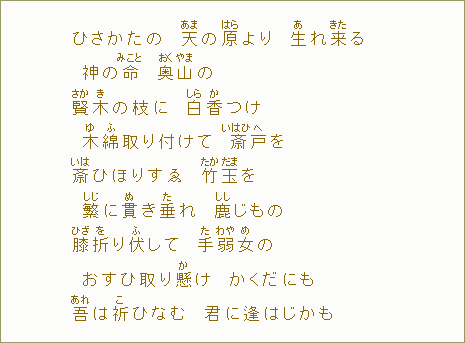図版[I]
図版[I] 図版[II]
図版[II] 新春の季、神社の境内では椿や山茶花の照り葉に合せて榊を観することができ、清らかさが漂ってきます。
その榊は、神社でのお祓いごととして榊に麻の木綿と四手(紙垂)の白紙を懸けたものと、榊に四手の白紙を懸けて玉串として神前に捧げるのに用いられ、そして各家の神棚飾りとして用いられる大切な木であります。そのお祓いと玉串の榊を図版[I]と[II]で参照にして見てください。
そして、その「さかき」の名前の由来は「栄樹・栄える木」から神に奉る・神の影向(神のお近づき)を得ることから「木の神」として銘ぜられたのです。その事柄は、奈良時代の『古事記』の「天の石屋戸こもり」の条から鑑することができます。
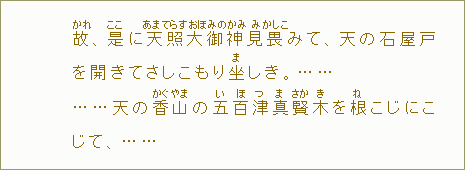
と詠ぜられ、天照の神は、弟にあたる須佐之男命から、荒荒しいふるまいを受けたことを恐れて、天上にある石屋戸にお隠れになられ、そのときから世の中は暗くなったのです。万の神々の英知により、大和の国で一番の美神で美声の「天宇受売命」に登場させて日影の葛に笹に定家葛、そして聖なる真賢木(榊)を大地から根こそぎ掘り取って、歓喜を高らかにあげながら舞ったのです。その異変に気付いた天照の神は、岩屋戸からお出ましになり、世が再び明るくなったのです。即ち榊は大和の国を再び栄えさせた木として重し銘せられたのです。
そして、『万葉集』では、「大伴坂上郎女、神を祭る歌」と題する長歌に
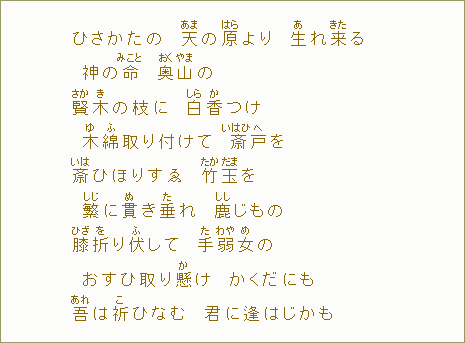
(天上の世界から生を受けついできた先祖の神に申しあげます。穢のない奥山の榊の枝に真っ白な木綿(楮・麻など白く晒した領巾や綿)を取りつけ、神に供えるための酒を盛る瓦笴(土器)の斎瓮(祭紀に用いる神聖な酒瓶)を慎んで土に掘りすえ、細い竹を輪切りにして緒に通した管玉飾りを沢山に垂らし、鹿の如く膝を折り伏せて、そしてさらに幅の広い布をそのまま肩にかけたりして、私はこれほどまでにもお祈りをしているのに、あの方にお逢いできないのでしょうか)と、大伴旅人が大納言となり九州の筑紫を離れられるので、神の依りつく依代・寄代の木である榊に逢瀬なる願いを祈して詠まれたものであります。

この歌の白香の木綿を思い入れて白綿を榊に懸け、白椿を出合せ
辰砂釉の四方瓶に挿けた作品を、そして榊の葉脇には影向色である黒実の懸けたれた姿も合せて参照して見てください。
また夏には白く可愛らしい花を咲かせます。
どうぞ、この初春には、神の依代である榊の緑々と照り輝く姿を観しては柏手を打ち、心清らかなる願い事を祈してみて下さい。