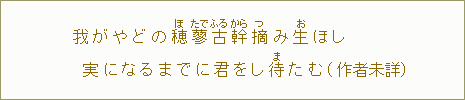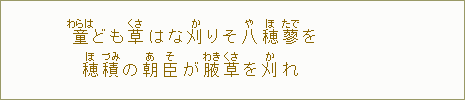晩秋の季、野や丘に草木の花の散る姿や、新たなる花の咲き薫う姿を観する出合いを楽しみますと、小ぢんまりとした池の端に、たわわに咲き薫ふ蓼の花と出合い、その細き花茎の白の小花の柳蓼の愛らしさに感銘をうけます。そして、また池の端から離れた所には、鮮やかな淡紅色の花の犬蓼との出合いがあります。
この蓼の花は、『万葉集』では三首詠まれており、その内の一首では、
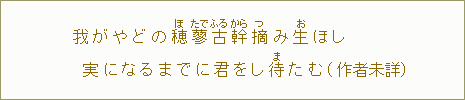
(わが家の穂蓼の古い茎から実を採んで育て、実がなるまで、あなたを待とう)と、食用としての実が熟すまであなたのことを待ちこがれると詠ぜられ、この「穂蓼」は花茎から白い花穂を出す姿から柳蓼を指すとされております。
そして、この歌は「古今相聞往来歌類の上」の「物に寄せて思いを陳ぶる歌」と称されており、往昔よりこの蓼の花は、食料や観賞として眺め愛され、さらに、その摘み取られた花に対しては、恋人との遭遇を念じていたのです。
そして、さらに次の歌では、草を刈り取っている少年たちに呼びかけての歌として、平群朝臣の嗤ふ歌一首として、
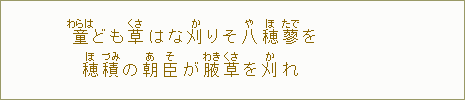
 図版[I]
図版[I]
(子供らよ、そこの草を刈らないでくれ、その代りに、あの穂積の朝臣のわきくさを刈れ)と詠ぜられ、この八穂蓼の花は、穂が多く出ることから、草刈りの効力が満たされることと思い入れて切々と詠われております。
この万葉時代に詠まれている蓼の花は、「柳蓼」であり、別名として(ほんたで、またで)と称されており、白色の花が
撓む茎から優美に咲き
薫います。
その白花の撓みの美しき柳蓼に、
菜摘みの時代
平籠に
藍蓼の花を出合せて、軽やかに
挿け上げた花を図版[I]を参照して見て下さい。
 図版[II]
図版[II]
そして、この花の別名としては「
真蓼、
水蓼、
本蓼」と称され、また、漢名としては「
蓼菜、
辣蓼、
蓼、
水蓼、
蓼穂、
蓼花、
川蓼」と数多の名が付されております。
そして、日本の最初の植物図鑑の『本草図譜』には「
蓼、たで」、別種として「やなぎたで、
辣蓼」と称され「はなはだ辛い香辛の蓼であり、漬物に用いられる」と記されており、図版[II]を参照して見て下さい。
どうぞ、この晩秋の季に、身近な池の端や小川のあたりに出向きて、可愛らしく咲き薫う柳蓼のみならず、桃色から赤色の蓼の花を
愛でて見て下さい。