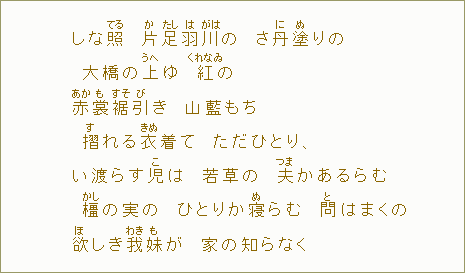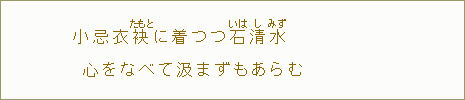春の中頃の季、神社や寺の境内の参道の脇の木下陰に、緑色の葉の先に小さな花穂を咲かせ、とき折りの風で柔らかに揺らぐ山藍の姿を観することがあります。
この山藍は、往昔より生葉を搗いて緑青の汁を取り、神事の折りの衣に摺り染めつけるものを「藍摺」「青摺」と平安時代の『延喜式』に称されております。
『万葉集』では、その山藍染めとして「河内の大橋を独り行く娘子を見る歌一首」と題した長歌に、
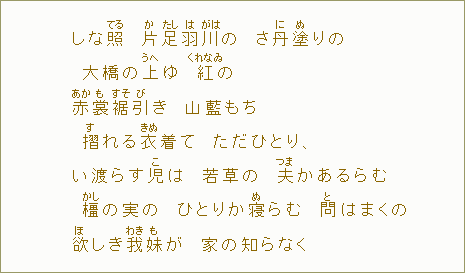
この長歌で「級照る」は片足羽川の地名の枕詞で、「若草の」は夫にかかる枕詞で、さらに「橿の実の」はひとりの枕詞であります。そして、歌意は(片足羽川にかかっている朱塗りの大橋の上から、紅染めの赤裳の裾を引き、山藍で染めた衣服をまとって、ただひとり美しい娘が渡ってくる。あの娘には夫がいるのだろうか、今夜もひとりで寝るのだろうか。問い尋ねてみたいけれども、あの娘の家も知らないことだからし方ないことよ)と、紅染めの裳裾に藍染めのすばらしい衣を着た娘を観することによってその魅力に取り付かれて、切々に詠まれています。
この魅力的な山藍染めは、平安時代になって「小忌衣」と称され、とり訳「笹・梅」の文の藍染めの衣は、「大嘗祭」や「新嘗祭」で着られる重要な祭り事の衣と相成り、その小忌衣の歌としては平安時代の藤原公任の『公任集』に藤原道長の歌として、
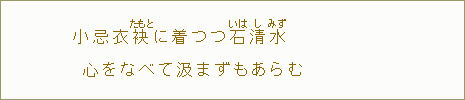
(山藍染めの袂衣としての小忌衣を着て、石清水に心のすべてかけて、清らかな水を汲みあげなければならないことよ)と歌われてります。こうした歌から、大切な山藍染めをもって、それを着ているときの、心のもちかたも高まりを高く感じ得ることができます。
その小忌衣の平安時代の図を、京都書房の『新国語総覧』を、図版[I]で参照して見て下さい。そして、もう一図は、神事の折りの舞の姿の図を『紀伊名所図会』の図版[II]を参照して見て下さい。
そのような、山藍に隈笹と菫を古代ペルシャの横線文カップ形土器に出合せて、挿けあげた作色を[III]で観して下さい。
どうぞ、この春の草木の花のたけなわの季、山野に生えている山藍の花咲き薫う自然の風姿を観し、折りに、葉を採しては摺り潰して、白き布やハンカチに摺り染めて、貴き願い事を成就させてみて下さい。