文化講座
翁草(おきなぐさ)「根都古具佐(ねつこぐさ)」
春の季を迎え、柔らかな日差しの中で、輝き咲いている翁草の花に出合うと、その姿が
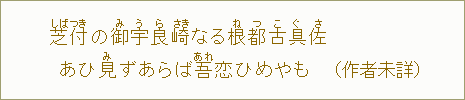 「芝付の
「芝付の
いったん「会い見てしまった以上は、翁草が地に根付くように、私の胸にある娘の面影が、焼き付いてしまった」と言う想いが込められています。
「万葉集」では、この一首だけ詠まれ、この歌は、第十四巻の
この翁草は、花に対して根が大きいことから「
根は、乾燥させて「
この翁草は、キンポウゲ科の多年草で、花丈が、十五センチから二十センチで、春に
又和名抄にも「

図版[I]
図でも、しっとりと咲く花、銀白色の糸状に垂れる実の翁草が、鮮明に描かれています。
しかし現在では、自生では、なかなか見られなくなっています。
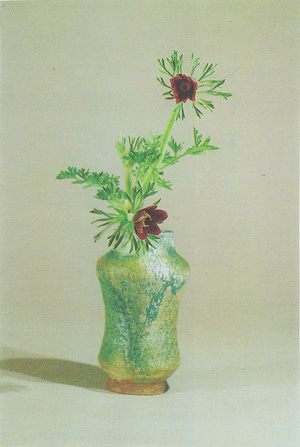
図版[II]
翁草の花の美しさ、根の付きようから、慕う人への思いをさらに深めた歌に心を込めて生けあげました。

