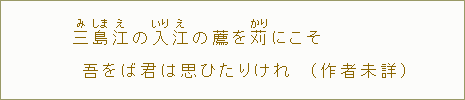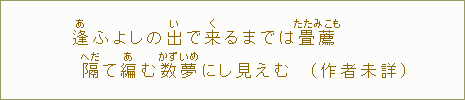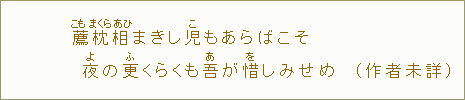秋も深まりゆく季、川や沼沢の辺を歩くと薄の片わらに、大きく撓めた葉の真中から赤紫色の穂花を凜と咲かせる真菰を観することができます。
この真菰の「こも」は、「禾の字音のクワ」と「裳の字訓のも」の合成転訛した語といわれ、上代の人々はやわらかな禾類の草を編んで衣裳つくりしたことから「禾裳」と呼称されたとされており、さらに、「食薦(食器の清なる敷物)」や「畳薦(多様なものの敷物)」や『薦枕(やすらぎを得るための枕)』などの暮しの具として賞愛されており、そのことから近世では「真菰草、勝見草、花勝見」と賞意の名が付され、さらに、薦の葉で粽を巻いたことから「粽草」とも呼称されております。
そして、『万葉集』では「薦、真薦、其母、茭、気米」の字が当てられており、そのうちの「薦」の字では、「刈薦」の歌が多く詠まれており、「古今相聞往来歌類の上」に所収、「物に寄せて思ひを陳ぶる歌」と前書きされ、
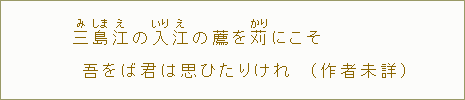
(三島江の入江の真菰を刈る かりそめにあなたは私を思っていたのですか)と歌われており、「相聞」とは「恋の歌」、「真菰を刈る」ことは「
仮る」ことと同音(音通)させてのもので、集中24首詠まれている真菰の中で「刈薦」は11首と多く、往時は「刈る」ことは「心の乱れ」や「思うことが叶わない」とした寓意を込めて詠われております。
そして、次の歌では、万葉人の暮しの身近な歌として、
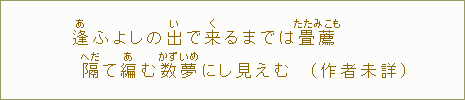
(逢うべき機会が訪れるまでは、せめて敷き薦の編目のように詰めて、幾度でもあなたの夢の中に現れましょう)と、薦畳のこまやかな編目の姿に比喩させて、恋しき人の夢の多さを切々と詠じております。
そして、さらに次の「薦枕」の歌では、「
挽歌」として、
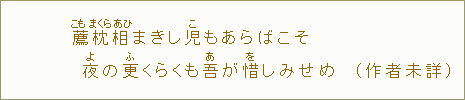
(真菰を枕にして共に寝たあの児も生きていればこそ、夜の更けてゆくことも私は惜しく思うだろうに)と、「挽歌」は「
黄泉の国の人への哀の歌」で、「
薦」と「
児も」の音通から、恋しき児(
妹・妻)と薦枕での共寝の深さを詠い挙げております。
その真菰は敷物としての賞愛だけではなく、種子や若芽は食用として、根汁は薬草ともされております。
そんな真菰に、可愛らしい秋の嫁菜を出合せて、古代朝鮮の
新羅高台付深鉢土器に、高らかと花穂を立て、左右に葉を大きく振り挿けた挿花を参照して見て下さい。
どうぞ、この深まりゆく秋季、川や池の堤を散歩しながら、真菰の花穂と葉の揺れ動く姿を観して、刈薦の意ならず、安らかなときを得て見て下さい。