文化講座
第2回 ロコモティブシンドローム
「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存知でしょうか。
ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ)とは、骨や関節、筋肉などの運動器の障害や、加齢に伴う衰えによって、歩行や立ち座りなどの日常生活に障害をきたした状態のことであり、ロコモティブシンドロームが進行すると要介護や寝たきりになるリスクが高まります。
第1回では、平均寿命の延びに健康寿命の延びが追いついていないのが現状であることをお伝えしましたが、このような超高齢社会を迎えた日本の未来を見据えて、2007年、日本整形外科学会によってロコモティブシンドロームという概念が提唱されました。
寝たきりや要介護の最も大きな原因として 、関節疾患・骨折・転倒などの運動器の障害や、高齢による衰弱が挙げられます。ロコモティブシンドロームを予防することが、健康寿命を延ばす大きな鍵となります。
まだ若いから大丈夫と思っているそこのあなた!驚くべきことに、40代の5人に4人はロコモティブシンドロームの予備群であるとも言われています。いつまでも自分の足で歩き続けていくためには、若いうちから運動器を健康に保ち、 ロコモティブシンドロームを予防することが大切なのです。
【ロコモティブシンドロームの原因】
ロコモティブシンドロームの原因には、①筋肉の量や神経活動の減少②関節軟骨や椎間板の減少③骨量の減少が挙げられますが、これらを放置すると、痛みや機能の低下による歩行障害をきたしてしまいます(図1)。
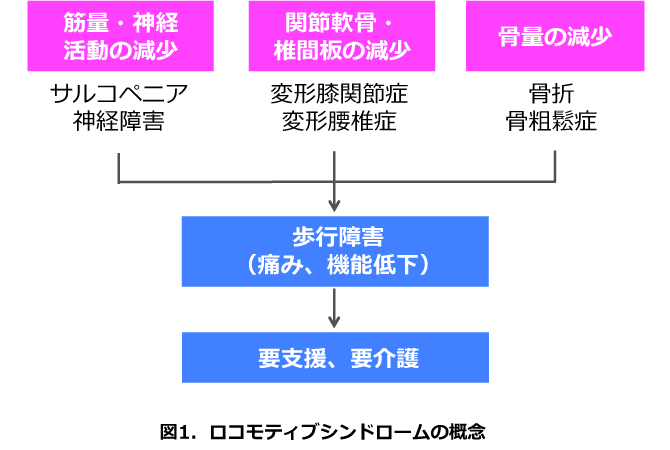
一般的に、筋肉や骨の量は20~30代がピーク。40代から次第に衰え始め、50歳を過ぎた頃から急激に低下します。特に、女性は男性よりも筋肉の量が少なく、閉経後には骨量が急激に減少します(図2、3)。 また、運動習慣のない生活を続けていると徐々に運動器が衰えてしまいます。
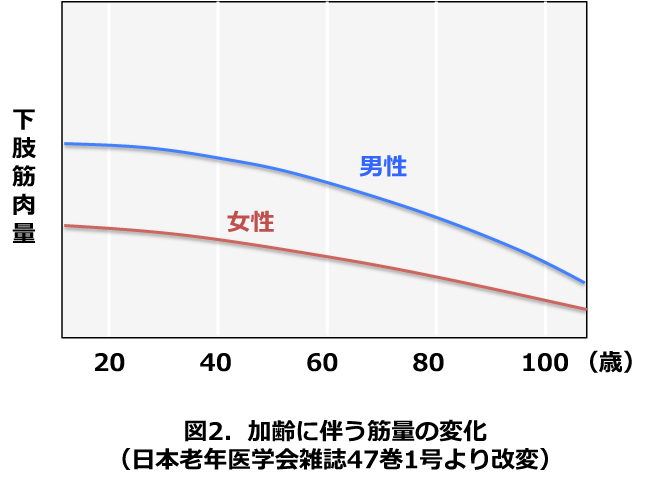
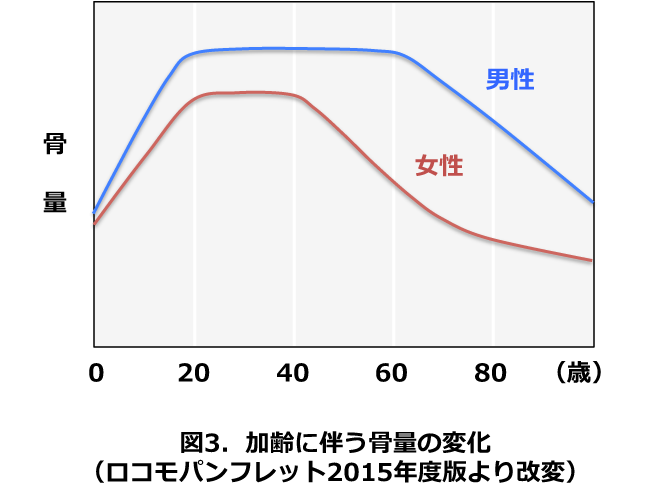
痩せすぎや肥満にも注意が必要です。女性の中には細い体がいいからと、筋肉を付けたくない人が多いかもしれませんが、痩せすぎると身体を支える骨や筋肉がどんどん弱くなります。また、筋肉が減るとエネルギー消費が減るため脂肪を蓄積しやすくなりますし、様々な病気のもとにもなるので、ある程度の筋量を維持することは健康維持だけでなく、美しさを保つためにも必要なのです。逆に太りすぎもよくありません。肥満は腰や膝の関節に大きな負担をかける上に、関節軟骨はすり減ると修復が難しい部分でもあります。
では、ロコモティブシンドロームを予防するためにはどうしたらいいのでしょうか。ポイントは、筋肉や骨を丈夫に維持するために十分な栄養を摂ることと、適度な運動で刺激を与えることです。
【筋肉を健康に維持する】
筋肉の量を増やし、筋力を高めるために最も重要な栄養素は、タンパク質です。タンパク質は20種類のアミノ酸から構成されていますが、体内で合成できないため食品中から摂らなければならないアミノ酸(必須アミノ酸)が9種類あります。動物性タンパク質の方が植物性タンパク質よりも吸収効率が優れていますが、含まれる必須アミノ酸が異なるため、両者を組み合わせて、さまざまな食品からタンパク質を摂りましょう。
タンパク質を多く含む食品:肉、魚、卵、乳製品、大豆製品など
また、タンパク質の分解や合成を促進する大切な栄養素であるビタミンB群や、エネルギー源となる炭水化物や脂質とともに摂ることで、筋肉の減少を予防しつつ、 筋肉をつくり、 効率良くエネルギーを生み出すことができます。
ビタミンBを多く含む食品:緑黄色野菜、レバー、鶏肉など
【骨を健康に維持する】
健康な骨を維持するために最も重要な栄養素は、カルシウムです。しかし、一般的に日本人はカルシウムが不足しがちです。骨粗鬆症を予防するためには、1日700〜800mgのカルシウムの摂取が推奨されているので、カルシウムが多く含まれる食品を積極的に摂りましょう。ちなみに、牛乳1本200mlに含まれるカルシウムは220mgです。1日1本の牛乳を飲む習慣をつけましょう。
カルシウムを多く含む食品:牛乳、小魚、緑黄色野菜、海藻類、大豆製品など
カルシウムの吸収を促進するビタミンDや、骨の形成を促進するビタミンKを併せて摂ると効果的です。また、夜21時から24時は、骨に沈着するカルシウムの量が最も多くなる時間帯ですので、夕食あるいは就寝前3時間から2時間前にカルシウムを摂取すると、より効率良く骨をつくることができます。
ビタミンDを多く含む食品:干し椎茸、鮭、卵など
ビタミンKを多く含む食品:ほうれん草、ブロッコリー、納豆など
【バランスの良い食事と運動でロコモ予防!】
日本整形外科学会は、以下の10の食品群のうち、できるだけ多くの食品を毎日食べることを推奨しています。
- 肉類
- 魚介類
- 卵
- 大豆、大豆製品
- 牛乳、乳製品
- 緑黄色野菜
- 海藻類
- 芋類
- 果物
- 油を使った料理
これらの食品をバランス良く食べることに加え、適度な運動をすることで、筋肉や骨を健康に維持し、ロコモティブシンドロームを予防しましょう。
【ロコモティブシンドローム予防のための献立例】

鶏肉・レバーとゆで卵の八角風味煮
鶏肉はひとくちくらいの大きさに切り、レバー、ゆで卵とともに、八角という中国香辛料、しょうゆ、砂糖で煮込んだ料理です。
- (栄養のポイント)
- 鶏肉やレバーは良質のタンパク質を含みます。
- 特にレバーは、ビタミンB群やミネラルを含み、疲労回復効果やカルシウムの吸収効率を高める効果があります。
切り干し大根とほうれん草のハリハリ
茹でた切り干し大根とほうれん草とキッチンバサミで千切りにした昆布をポン酢しょうゆで和えるだけの簡単メニューです。切り干し大根の食感を残すとハリハリ(シャキシャキ)と美味しいです。
- (栄養のポイント)
- 切り干し大根とほうれん草にはビタミンB、ビタミンC、カルシウムが豊富に含まれます。
- 食物繊維が豊富なので、腸内環境を整えます。
けんちん汁
豆腐、ごぼう、にんじん、里芋などをごま油で炒め、かつおだしを加えて煮込み、しょうゆで味付けした汁料理です。
- (栄養のポイント)
- タンパク質(豆腐)と、野菜をバランスよく食べられます。
- かつおだしはミネラルとビタミンBが豊富であるうえ、発酵食品なので、食物繊維の多い野菜類とともに、腸内環境を整えます。

