文化講座
第53回 バッハの墓参とライプツィヒ弦楽四重奏団演奏会・ゲーテ Goethe「Faust」ゆかりの最古の酒場アウアーバッハス・ケラー Auerbachs Kellerを巡る

バッハゆかりの聖トーマス教会
私がこの愛知県共済の「旅」連載を始める以前に、私は35日間ほどドイツ、イギリス、フランスを好きなように、自由気ままに歩いてきました。前回はドイツに来て初めての快晴の秋の一日、鉄道でヴァイセンフェルスにあります哲学者ニーチェ(Friedrich Nietzsche)の生家を訪れ、墓参を済ませた様子を書きました。
今回の原稿は、その日の午後に古都ライプツィヒに戻り、作曲家バッハが活躍しました聖トーマス教会などを訪ねた1日の終わりに書いたメモを元に書きました。
バッハが1723年から1750年まで音楽監督を務め、あの有名な「マタイ受難曲」や平均年間50曲の作曲と演奏を行ったことで知られる有名な教会です。
年間で平均50曲を作曲したということは、日曜日のミサの度にオリジナル曲を作曲していたということになり、ものすごいスピードで作曲していたことになります。大変なことと言わざるを得ません。バッハの生真面目さがよく出ています。その他にも「器楽曲」を作曲してましたから、もう泉のごとく曲が涌き出てきたのでしょうね。驚くべき才能は「音楽の父」といわれてますが、「音楽の神」の方がふさわしいといえる方です。
私は高校の時に、オルガン音楽やコレルリの合奏曲が好きになり、その流れでヴィヴァルディやバッハを聴くようになり、そこから急速にバッハに魅かれました。特に無伴奏チェロ組曲や無伴奏ヴァイオリンソナタに惚れ込み、傾倒しました。
その他どのようなバッハの曲も好きですが、特にヴァイオリンがレオニード・コーガン、チェンバロがカール・リヒターの「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ」などはとりわけすばらしい曲だと思い、いまでも愛聴しています。
さらにブランデンブルク協奏曲も好きでレコードを収集しました。現在まで詳しいリストを作成してませんが、この曲だけで、指揮者・楽団の違う古今のSPからLP・CD録音まで、初期から100セット以上はあると思います。海外の中古レコードショップにまで手紙を出したりして、指揮者、演奏家により違うレコードを求めました。
とりわけ私が一番バッハの作品で、心洗われるオルガン曲は、コラールプレリュード≪主イエス・キリスト、われ汝を呼ぶ≫ BWV639番です。この曲は、ロシアの、というより世界の名画監督アンドレイ・タルコフスキーの世界最高傑作SF名画「惑星ソラリス」(ちなみに他の監督も制作してますが、問題にならないくらい、タルコフスキー監督の作品が優れています。不朽の名作です)のテーマ音楽に使われた名曲です。私はこの難解な映画「惑星ソラリス」につきましては、日本語、英語とドイツ語で「論文」を書きましたから、いつかまた公開させていただきたいと思っています。

中央祭壇前のバッハの墓所
今回はそのバッハが活躍した念願の聖トーマス教会を訪れ、彼の墓参をすることができました。教会の中にある祭壇前の質素でバッハらしいお墓です。13年間連れ添った最初の妻に先立たれた後、再婚したアンナ・マグダレーナは16歳年下でしたが、貧しい生活の中、献身的にバッハを支えました。きっとお裁縫も精魂込めてしたのでしょう、彼女の小さな指ぬきもバッハの棺の中に一緒に埋葬されていました。来世でも、着物を作り続けますという彼女の愛のささやかな証で、心打たれます。
聖トーマス教会は思ったより小さい教会で、横にはバッハの立派な銅像が立っています。
今回は偶然、トーマス教会合唱団とオルガンの演奏会がその日4時からあると聞いて、急いで申し込むと席がとれました。バッハが演奏したオルガンを聴くことができました。
トーマス教会合唱団(Thomanerchor)は、市内最古の音楽団体です(1212年創設)。その歌声はまさに天使の歌声です。教会の空間に響いて、それはとても素晴らしいものでした。曲はもちろんバッハのカンタータが中心でした。
夜にはメンデルスゾーン記念ホールでのライプツィヒ弦楽四重奏団の演奏会に行く予定でしたが、まだ十分時間がありました。
聖トーマス教会の音楽をたっぷりと堪能して、8時開演の弦楽四重奏を聴きに、名門ゲバントハウスのメンデルスゾーン・ホールに向かいました。
夜で暗かったのですが地図を頼りになんとかわかりました。かなり早く着いたのですが、すでに会場には担当者がいて、案内してくれました。「どこから来たのですか?」「日本からです」「おお、それはありがとうございます。それでは一番前の真ん中にお座りください」ということで最高の席に案内されました。近すぎる感じもありましたが、こうしたことはめったにないことですから、好意に甘えました。世界的なコンサートで、こんなに間近に、座ったことはありません。演奏者から2メートルくらいの席です。まるで楽団員の中で聴いてるみたいです。
今夜のテーマは「ライプツィヒ弦楽四重奏団・週末の室内楽の夕べ」と題して、曲目は以下の通りです。
アマデウス・モーツァルト 弦楽四重奏 KV465
アンドレアス・ロンベルグ 弦楽四重奏 NR.2
フランツ・シューベルト 弦楽四重奏 D804(ロザムンデ)
演奏者は
ヴァイオリン:Stefan Arzberger
ヴァイオリン:Tilman Buening
ヴィオラ:Ivo Bauer
チェロ:Matthias Moosdorf
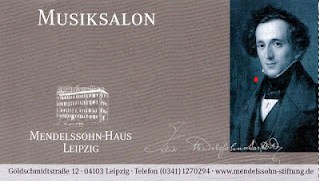
ライプチ弦楽四重奏団の当日の入場券の写真
ライプツィヒ弦楽四重奏団は1988年にあのフルトヴェングラーで有名なゲバントハウス・フィルハーモニーの中から選りすぐりの四人によって結成された弦楽四重奏団なのです。 私はゲバントハウス・フィルのコンサートを聴きたいなと思ってインターネットで調べたところ、この近辺の日程では演奏会がなくて、弦楽四重奏があるのを見て予約したのです。それも非常に安くて、15ユーロ、日本円に換算して当時の1600円弱という金額でした。世界的な弦楽四重奏団の演奏がです。楽しみにしていました。しかも一番前に座らせてもらえるとは思いませんでした。
演奏は思った通りに素晴らしいものでした。真ん前で、まるで私のために演奏してくれているかのようです。一番前の真ん中ですから前に観客がいないのでそう思うのもしかたありません。やはりこの迫力と音質は感動ものです。我を忘れる夢のような2時間があっという間に過ぎました。大満足でした。日常的にこうした演奏会をたのしめて、ライプツィヒの人たちは幸せだなぁと思いました。こんなに素晴らしい世界的な演奏者たちの演奏会を気軽に、安い金額でいつも楽しめるのですから...。
朝食を済ませてから食事をとってませんから、帰りにあまりの空腹になったので、ゲーテゆかりの地下酒蔵、アウアーバッハス・ケラー(Auerbachs Keller)で軽く食事をとることにしました。
この酒場はゲーテの時代(18世紀中ごろから19世紀初めころ)からライプツィヒ大学の学生たちに愛されて現在に至ります。ゲーテの代表作「ファウスト」にも登場します。こんなに古い酒場は日本にはありません。本当に羨ましいです。
ケラーとは地下の酒蔵のことですが、1階の店の入り口にメフィストがファウストを酒場に誘っている場面の銅像があります。

ファウストを誘うメフィスト
ケラーに来たからにはビールを注文せねばならないのですが、ここの名物のオニオンスープを注文し、バンベルグのラオホビールが美味しかったので、これはないかと聞いてみました。

ビールにオニオンスープ
すると「ここはライプツィヒだからライプツィヒのビールを飲め」といって笑うので、では任せるからうまいのを頼む、と言うとヤボール「Jawohl」(もちろん)との返事。なかなか気持ち良い、フロア主任のいい男です。早速運ばれてきたのが、樽から注がれたばかりの、まさに生ビール。「ウ~、うまいなぁ~!」あまりの美味しさに、つい声に出てしまいました。冷たくてすっきりしたビールは空腹の五臓六腑に沁みわたりました。続いて出たオニオンスープ。2か所のコンサートを優先させて、いつもの昼食兼夜食をもとらずにいたので、お腹ペコペコでしたから、これも出来立て、熱くてうまい、幸せです。おいしい食事を楽しませてくれた親切なフロア主任にチップをはずみました。
こうして、今日はかねてから念願であったニーチェの故郷と墓を訪れることと、バッハの聖トーマス教会と墓を詣でることが実現し、ライプツィヒ滞在の大きな目的を果たせました。そして聖トーマス教会のオルガンと合唱の夕べのコンサートを聴くこともできて、本当に幸せでした。更に、素晴らしいゲバントハウス弦楽四重奏を真ん前で楽しめ、さらにさらにゲーテのファウストゆかりのケラーでおいしいビールとオニオンスープを楽しめるなんて、天気も良くて大満足、最高の一日でした。

バッハゆかりの聖トーマス教会
※こちらをクリックされますと、同じ著者による「掌の骨董」にアクセスできます。併せてお楽しみください。

