文化講座
第11回:「マレーシアの長寿食」について学びます。
前シリーズでは「日本食って素晴らしい!」と題し、日本食の代表である「天ぷら」「寿司」「餅」「蕎麦」など、国内外で人気のある日本食についてご紹介してきました。
今シリーズは、「世界の長寿食」というテーマで、世界各地の人々は健康を維持するために何を食べてきたのかという背景を探りつつ、それらの料理を日本でも手に入る食材を使ったレシピで紹介したり、含まれる栄養素の効能についてもお伝えしております。
第11回目のテーマは、「マレーシアの長寿食」です。
WHO(世界保健機関)が発表した2023年世界の長寿ランキングによると、マレーシアは世界第80位、平均寿命74.7歳の国です。マレーシアの人々はどんな料理を食べているのでしょうか?
※ちなみに世界全体の平均寿命は72.5歳、世界最長寿の国は日本で、平均寿命は84.3歳です。
マレーシアの概要
| 面積: | 33万km2(日本の面積の約0.9倍) |
|---|---|
| 人口: | 約3,350万人(2023年現在) |
| 首都: | クアラルンプール |
| 宗教: | イスラム教(連邦の宗教)64%、仏教19%、キリスト教9%、ヒンドゥー教6%、その他2% |
| 言語: | マレー語、中国語、タミール語、英語 |
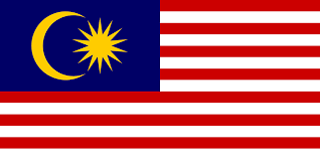
マレーシアの国旗
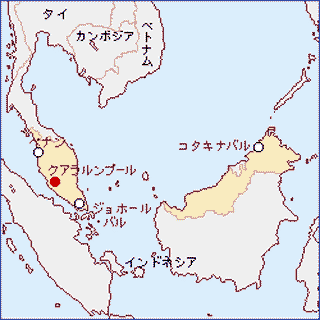
マレーシアってどんな国?
正式名称はマレーシアですが、連邦制国家であることを鑑みマレーシア連邦とされることもあります。
マレーシアは、マレー半島とボルネオ島の一部を領域とする東南アジアの国です。ビーチと熱帯雨林があり、マレー、中国、インド、ヨーロッパの文化的影響が混ざり合った国として知られています。首都クアラルンプールには、植民地時代の建物や、ブキッビンタンなどの賑やかなショッピングエリア、象徴的な高さ451mのペトロナスツインタワーなどの超高層ビルがあります。
年間の日中平均気温は27~33℃、年較差は1~2℃で年間を通じて変化があまりなく、比較的カラッとしており日本の夏のような不快感はなく、特に朝晩は涼しく、過ごしやすい気候です。
多民族国家であり、マレー系(約6割)・中国系(約3割)・インド系(約1割)、先住民族と、マレーシア特有の「多様性」を生み出し、多様性ゆえの様々なグルメを楽しめるのもマレーシアの魅力です。
のんびりとくつろぐことの出来る砂浜、南国の熱帯雨林、魅力的な島々、神秘的で荘厳な山々など自然美に溢れる国です。
マレーシア料理の特徴
複数の民族がともに暮らすマレーシアの料理は、驚くほどバラエティに富んでいます。
スパイシー(辛い)です。タイ料理・インド料理・中国料理がミックスされたような味です。
調味料も同様にミックスされたものが多くあります。多民族なので混ざった料理が多いですが、地方によって味も調味料も異なります。
- ココナッツミルクとスパイスのマレー料理
- 点心から麺まで多種多彩な中国料理
- 香り豊かなカレー文化のインド料理
- マレーシア発祥のニョニャ料理
この4つのグループを中心に広がる多彩な味は、多文化が共存するマレーシアそのものです。ちなみに、マレーシアでいちばんポピュラーな挨拶は「スダマカン?」。ご飯食べた?という意味で、それほど食文化が生活の中心にあることを表しています。
マレーシアの料理は多食材を使用すること・発酵食品なども入れて複雑な味わいがすること・各種の栄養素が整いやすい点・食に対する意識が貪欲であることなどの点が、健康維持に役立っていると考えられます。
マレー料理
ココナッツミルクをよく使う料理です。加えて、唐辛子の辛み、パンダンリーフやターメリックなどのハーブの香り、タマリンドの酸味を効かせます。じっくり時間をかけて煮込み、コク深い味に仕上げる料理が多いのは、ご飯に合わせて食べるのが基本スタイルのため。辛みは、あとからジワッとくるタイプです。また、おもにイスラム教徒であるマレー人向けの味なので、料理に豚肉と酒を使わない「ハラル」の調理法に則っています。代表的な料理は、サテー、ナシゴレン、ナシレマ、チキンカレー(カリアヤム)。ABC(伝統的なかき氷)やピサンゴレン(バナナ揚げ)などのデザートも充実しています。
サテー
屋台料理の定番はサテー。レモングラスやターメリックで下味をつけた肉を串に刺し、炭火でこんがり焼いたもの。コク深い甘辛のピーナッツソースをかけて食べます。鶏肉が一番ポピュラーで、牛肉、羊肉のサテーも人気です。

サテー
現地撮影:伊藤華づ枝
ナシゴレン
ナシ=ご飯、ゴレン=炒めるで、つまりは炒飯のこと。店によって具や味つけはさまざまで、唐辛子で辛くするのが主流です。目玉焼きをのせ、さらに唐辛子醤油(チリパディ醤油)で辛味を加えながら食べると一層美味しいです。

ナシゴレン
料理作成・撮影:伊藤華づ枝
ナシレマ
マレーシア人のソウルフード。ココナッツミルクで炊いた香りの良いご飯に、サンバル(チリソース)を混ぜて食べます。ゆで卵、きゅうり、ピーナッツ、小魚が添えられていて、唐揚げやカレーを追加することも。朝食の定番です。

ナシレマ
筆者が現地で作成した料理
中国料理
おもに19世紀に渡ってきた中国移民によって、マレーシア料理は世界でも稀にみるバラエティに富んだものになりました。彼らのルーツは多岐にわたっていたため、ひとことに中国料理といってもさまざまな味があります。広東、客家、潮州、福建などで、とくに広東の流れをくんだ点心文化は、本場顔負けの本格派。今やマレーシアの食文化として、民族の垣根を超えて親しまれています。マレーシアで発展を遂げた料理も多く、代表的な料理は、バクテー、チキンライス、ヨントウフ(マレーシア風おでん)・パミー(麺料理)、チャークイティオなど麺料理もバラエティ豊かです。
バクテー(肉骨茶)
中国漢方で豚肉をじっくり煮込んだスープ料理です。滋養強壮に効果があるといわれ、中国系マレーシア人のスタミナ源。豚肉は、骨付き、内臓系など、好みの部位が選べます。意外にもクセの少ない味で、ご飯によく合います。

チキンライス
東南アジアの定番料理チキンライスは、マレーシアでも人気です。ゆで鶏と鶏スープで炊いたご飯のコンビで、チリソースや生姜ソースをかけて食べます。最近はスパイスを効かせたマレー系の「ナシアヤム(チキンライス)」もポピュラーです。

チャークイティオ
チャー=炒める、クイティオ=米麺で、香ばしく米麺を炒めた料理です。具は海老、野菜、カリカリの豚の脂身などで、もっちりした米麺の食感が特徴。マレーシア全土で食べられますが、とくにペナンのチャークイティオが有名です。

インド料理
おもに19世紀、英国統治時代に移り住んだインド移民が持ちこんだ料理です。南インド出身者が多かったことから、南インドのミールスそっくりのバナナリーフカレーがマレーシア各地で食べられます。また、タンドリーチキンもポピュラー。常夏の気候にカレー文化は非常にマッチし、今では民族を問わず、マレーシア人はカレーが大好き。ロティチャナイ、トーサイ(クレープのような生地の軽食)、ビリヤニ(スパイスの炊き込みご飯)、テタレ(ミルクティー)はインドをルーツとしますが、もはや国民食といってもいいほど多数のカレーが並んだナシカンダールも万人に支持されています。
ロティチャナイ
マレーシアの定番の朝食。薄くのばした小麦粉の生地を層にして焼いたもので、カレーソースで食べます。インド系の食堂では、注文後に職人が生地を伸ばすところから手作りしていて、モチッ&サクッとした焼きたてを提供しています。

タンドリーチキン
おなじみのインド料理=タンドリーチキンは、マレーシアで手軽に食べることができます。それもヨーグルトやスパイスに漬け込んだ鶏肉をタンドリー窯で焼き上げる本格派。食堂や屋台で手ごろな値段で提供されています。

バナナリーフカレー
バナナの葉を皿にして、カレーやおかずを盛り付けたカレーセットです。おかずの種類は店によってそれぞれで、カレーは汁のみで具はありません。チキンカレーや唐揚げなどを食べたい場合は、追加でオーダーできます。

ニョニャ料理
15世紀から中国人男性がマレー半島に移り住み、現地の女性と結婚して生みだしたのがニョニャ料理です。彼らの子孫のうち男性をババ、女性をニョニャと呼ぶことが料理名の由来で、東西貿易で栄えたマラッカ発祥の味です。特徴は、マレー半島で好まれるハーブやココナッツミルクに、豆腐や干し椎茸などの中国食材を加えること。多数の食材と工程を必要とする凝った料理が多く、一度食べると虜になります。オタオタ、パイティーなどの前菜、ニョニャ・ラクサ、ウダン・ルマッ・ナナスなどの煮込み料理、カラフルなニョニャ・クエなど種類豊富なのも特徴です。
パイティー
ニョニャ料理で人気の前菜です。カリッと揚げたひとくちサイズのカップに、海老や野菜、卵焼きなどが入っていて、チリソースをつけて食べます。口のなかで、外側のパリパリ食感やさまざまな具の味覚が弾けます。

パイティー
筆者が現地で作成した料理
オタオタ
マレーシア版のかまぼこです。魚のすり身に、ココナッツミルクやスパイスを加え、バナナの葉に包んで蒸し焼きにします。東南アジアらしい香りが特徴で、辛くないので食べやすさもうれしいです。マレー系の屋台でも提供されています。

ウダン・ルマッ・ナナス
海老とパイナップルの煮込みです。スープのベースはまろやかなココナッツミルクで、パイナップルの甘酸っぱさと唐辛子の辛味を加え、レモングラスとターメリックで香りをつけた魅惑の味。ご飯と一緒に食べるとハマります。

マレーシアの伝統菓子
マレーシアの伝統菓子といえば、Nyonya Kuih(ニョニャ・クエ)です。甘いものが大好きなマレーシア人。午後になるとクエ(クエはお菓子という意味)を置いているカフェは、お茶とクエを楽しむマレーシア人で賑わいます。
クエは、日本の和菓子に似ています。米やタピオカ、ココナッツ、ココナッツミルクやパンダン(東南アジアに生息するタコノキ科の植物。バニラの香りに似た甘い香りを放ち、緑の着色などに使われる)を使用したカラフルな菓子です。あまりにもカラフルで一瞬ギョッとしますが、花や植物などの天然色素を使って色付けしているので安心です。

オンデオンデ
黒糖蜜の入った生菓子。パンダンリーフで緑色に着色した餅で、グラマラッカ(黒糖)の破片を包み込み、ココナッツフレークとゴマをトッピングして作ります。中に包んだ黒糖蜜が、時間経過と共に餅に吸収されるので出来たてから数時間以内に食べてしまいたい新鮮勝負のスイーツです。
オンデオンデを食べたとき、ジュワッと出てくる黒蜜の正体はグラマラッカと呼ばれる、ココナッツの樹液を煮て固めた天然黒糖。常温では固形なのですが、オンデオンデ調理過程で餅を茹でる作業があり加熱されることにより黒糖蜜に変化します。ニョニャスイーツの中でも人気の高いオンデオンデは出来立てが美味しい。
オンデオンデというお菓子はシンガポールでも見ることができ、これらの国ではココナッツを周りにまぶしてあるものが一般的です。東南アジア各国に移住した華僑の人々が伝えた食文化の発展形だと言えます。
 オンデオンデ
オンデオンデ
料理作成・撮影:伊藤華づ枝
サンバルとは
サンバルは香辛料や香味野菜、発酵調味料を混合して作った一種の「和え衣・ソース」で、野菜や魚介類を和えて食べます。和え物自体をサンバルというときもあるようです。
サンバルの基本は、唐辛子、バラン・メラ(小タマネギ)、レモングラス、ガランガー(ショウガのようなもの)、ターメリック、大豆の醗酵ペースト、タマリンド(マメ科の植物)、トマトピューレ、塩、こしょう、化学調味料などを混ぜ合わせたもので、ペースト状です。
 ハーブ類を石製のすり鉢ですり潰してサンバルを作ります。
ハーブ類を石製のすり鉢ですり潰してサンバルを作ります。

マレーシアの料理教室で現地人から料理を習っている筆者
代表的なマレーシアの料理2点を紹介します
オンデオンデ~マレーシアの伝統的な生菓子~

| 材料 | 約20個分 | |
|---|---|---|
| さつまいも(皮付き) | 250g | |
| 白玉粉 | 30g | |
| 水 | ~30ml~ | |
| もち粉 | 100g | |
| 砂糖 | 20g | |
| 水 | ~80ml~ | |
| パームシュガー(又は黒砂糖) | 50g | |
| ココナッツファイン | 50g | |
作り方
- さつまいもは厚めに皮をむいて1㎝位の輪切りにし、柔らかくなるまで蒸します。(約10分)
- 1.を熱いうちに裏ごしして冷まします。(裏ごしすると230g位になります)
- ボウルに白玉粉を入れて分量の水を少しずつ加えながら練り、ひとかたまりにします。
- 大きなボウルにもち粉、砂糖、2.、3.を入れてさっくりと混ぜ合わせ、水を少しずつ加えて練ります。(耳たぶくらいの固さにします)
- 4.を20等分(1個20g位)にし、細かく刻んだパームシュガーを包んで丸めます。
- 5.を熱湯で浮いてくるまで茹で(約3分)、水気を切ってココナッツファインをまぶします。
※写真は紫芋を使いました
ナシゴレン~マレーシアのエスニックチャーハン~

※マレーシアやインドネシア料理のひとつで、辛味のきいた焼き飯風の料理です
| 材料 | 4人分 | |
|---|---|---|
| むきエビ | 12尾(140g) | |
| 鶏ささみ | 3本(200g) | |
| 酒 | 大さじ1 | |
| 油 | 大さじ3 | |
| A | 玉ねぎ(みじん切り) | 1/2コ(120g) |
| にんにく(みじん切り) | 小さじ1 | |
| しょうが(みじん切り) | 小さじ2 | |
| 干しエビ(水で戻してみじん切り) | 大さじ1~2 | |
| 赤パプリカ | 1/3個(80g) | |
| ピーマン | 2個 | |
| 塩 | 小さじ1/2 | |
| こしょう | 少々 | |
| ご飯 | 800~900g | |
| 塩 | 小さじ1/3~ | |
| ナンプラー | 大さじ2~3 | |
| 赤唐辛子(種を出してみじん切り) | 1~2本 | |
| 卵 | 4個 | |
| 季節の野菜 きゅうり・紫玉ねぎ・ライム・パクチーなど |
適量 | |
作り方
- エビは酒と塩でもみ洗いし、洗い流してから茹でます。
- 鶏ささみは筋を取り除き、5~7mm角に切って酒をまぶします。
- フライパンに油を入れ、油がぬるいうちに(A)を入れて炒めます。
- 良い香りがしたら、2.の鶏肉を入れて炒め、表面の色が変わったら赤パプリカとピーマンを加えて、鶏肉に火が通るまで炒めます。
- 4.に塩とこしょうを振って下味をつけてから、ご飯をほぐすように炒め、更に塩を追加して調味します。
- 5.に鍋肌からナンプラーを加え、仕上げに赤唐辛子と1.のエビを加えてサッと混ぜます。味を見て、再び塩かナンプラーで味を整えます。
- フライパンかレンジで目玉焼きを作ります。野菜を適宜用意します。
- 器に6.~7.を彩りよく盛ります。
※写真にはえびせんべいを添えました

