文化講座
第6回:「おでん」について学びます
前シリーズでは「私は麺食い人!」と題し、日本独自の発展を遂げたラーメンを始め、アジア各国の食文化ともつながりの深い麺料理など、バラエティに富んだ麺料理をご紹介しました。
今シリーズでは、「日本食って素晴らしい!」というテーマで、日本食の代表である「天ぷら」「寿司」「餅」「蕎麦」など、国内外で人気のある日本食についてご紹介いたします。
「和食」がユネスコ無形文化遺産になって来年で10年目を迎えます。普段、私たちが食べている「日本食」の素晴らしさを一緒に再確認していきましょう。
第6回目のテーマは、「おでん」
1月20日は大寒。一年で最も寒さが厳しい時期です。そんな時には熱々の「おでん」が食べたくなりますね。
今回はおでんの中でも「関東煮」と「味噌おでん」について紹介します。
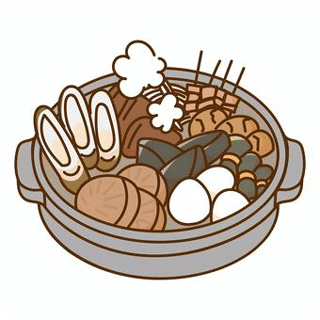
おでんとは
鰹節と昆布でとった出汁に味をつけ、種と呼ばれる様々な具材を入れて長時間煮込む料理のことです。
おでん種としては、さつま揚げ、焼きちくわ、つみれ、こんにゃく、大根、芋、がんもどき、牛すじ、ゆで卵、厚揚げなど地域や家庭によって異なります。
「おでん」は、田楽から名付けられた言葉で、田楽に「御」を付けて丁寧にし、田楽を省略して「御田(おでん)」となりました。
おでんのルーツ
「田楽」とは、もともと田植え時の豊穣祈願の「田楽舞」のことで笛や太鼓のリズムに合わせ一本の竹馬に乗って踊ります。拍子木型に切った豆腐に竹串を打って焼く形が田楽舞に似ていることから「田楽」の名が付きました。
田楽や味噌田楽は室町時代に出現した料理で、種を串刺しにして焼いた「焼き田楽」や種を煮込んだ「煮込み田楽」がありました。
江戸後期には江戸近郊の銚子や野田で醤油の醸造が盛んになり、安い醤油が庶民にも行き渡るようになりました。焼き上がりを待てないせっかちな江戸っ子のために、温めて味噌を塗る手間がかかる田楽より、「早くてうまい」醤油味の煮込みおでんが生まれました。
この時代から「おでん」は「煮込み田楽」を指すようになり、「田楽」は「焼き田楽」を指すようになりました。

豆腐田楽(写真:伊藤華づ枝作)
江戸時代は田楽の種類が豊富に
江戸時代になると、豆腐田楽は庶民の間でも食べられるようになり江戸の名物となりました。
街道沿いには「飯屋」が多くなり、餅や田楽、煮しめなどを売る店が増え、居酒屋・うどん屋・鰻屋・団子屋・そば屋などが賑わい、田楽の種類も豆腐だけでなく、こんにゃくや野菜類、魚類と増えていきました。
おでんと燗酒
外食産業が盛んであった江戸では、おでんの振り売りは「おでん鍋」と「燗鍋」を乗せた木箱に天秤棒を渡し「おでんかんざけ」の行灯やのれんをかけ「おでん燗酒、甘いと辛い、あんばいよしよし」と呼び声をかけて、街を売り歩きました。
串に刺した田楽はファストフード感覚の手軽さで、単身者が多かった江戸で人気を集めました。
各地のおでん
日本各地にはその地域ならではの様々なおでんがあり、気候に合わせた工夫や特産品が入っています。代表的なおでんを紹介します。
札幌おでん
特産の昆布を使った昆布だしに、海と山の幸が入ったおでんです。
フキやホタテ、タラの白子が入ります。「マフラー」と呼ばれる四角く長いさつま揚げも定番です。
青森おでん
生姜入り味噌だれを付けて食べます。
寒い冬に体を温めるため、味噌に生姜をすりおろしたものを入れたタレを使うようになったのが由来です。
ホタテやたけのこ、白こんにゃくが入ります。

青森おでん
小田原おでん
かつおと昆布に塩のみとシンプルな出汁に、小田原特産の梅を使った「梅みそ」を付けます。
すじ(魚の練り物)、つみれ、ちくわ、厚揚げなどたっぷりの練り物を入れます。
静岡おでん
だし粉(いわしやかつおの粉と青のり)をかけて食べます。
名物の黒はんぺんやなると巻、豚もつを入れます。
金沢おでん
昆布がきいたあっさりした出汁で作ります。
カニ面(甲羅に身を詰めたもの)・車麩・つぶ貝・赤巻(渦巻き状の練り物)が入ります。

金沢おでんは名物「かに面」が入ります
名古屋おでん(味噌おでん)
みそダレにつけて食べるものと、みそ仕立てのだし汁で煮込むものがあります。
詳細説明と「赤みそ煮込みおでん」レシピは下記を参照下さい。
関東煮
関東煮とは関西でのおでんの呼び名です。
詳細説明と「関東煮」レシピは下記を参照下さい。
姫路おでん
醤油に生姜を溶かしたタレを付けて食べます。牛すじやごぼう巻きを入れます。
沖縄おでん
豚骨ベースの出汁で作ります。豚足・青菜・ウインナーが入ります。
関東煮
関東煮とは関西でのおでんの呼び名です。おでんは日本全国に共通する料理の名前というわけではなく、関西地方ではおでんのことを「関東煮」または「関東炊き」と呼ぶことがあります。
なぜ関西ではおでんのことを関東煮(関東炊き)と呼ぶのかは諸説あり、関東発祥の煮物だからという説や関東大震災によって移住してきた関東人が関西に広めたという説、また江戸時代に関西を訪れた中国人が広め「広東煮(かんとんに)」という読み方が変化して関東煮になったという説などさまざまあります。
それでは、おでん(関東煮)を紹介します。
おでん(関東煮)

| 材料 | 4人分 | |
|---|---|---|
| 大根(2~3cm厚さ) | 4切れ(400~500g) | |
| 里芋(中・又はじゃがいも) | 4コ(200g) | |
| 板こんにゃく | 1/2丁 | |
| ちくわ | 2本 | |
| 揚げはんぺん | 4枚 | |
| 油揚げ(6~7cm角) | 4枚 | |
| 切り餅 | 2コ | |
| かんぴょう(20cm) | 4本 | |
| 卵(ゆで) | 4コ | |
| 日高昆布 | 1枚(15~20g) | |
| 牛すじ(国産) | 150g | |
| ゆでタコ | 80g | |
| 竹串 | 12本 | |
| 花かつお | 多め | |
| A | みりん | 大さじ3 |
| 酒 | 大さじ3 | |
| しょうゆ(又は薄口しょうゆ) | 50~60ml | |
| 砂糖 | 大さじ1 | |
| にんじん(梅花・ゆでる) | 8枚 | |
| マスタード(洋辛子) | 適量 | |
作り方
- 大根は皮を丸むきし、面取りします。裏側に十文字の切り目(隠し包丁)を入れ、あれば米のとぎ汁で柔らかくなるまでゆでます(沸騰後10~15分)。
- 里芋は皮をむいて下ゆでします(9分通りゆでます)。
- こんにゃくは下ゆでし、ななめ半分に切り、更に2枚に薄く切って片面に碁盤目に切り込みを入れ串に刺します。
- ちくわは半分に切ります。はんぺんはそのまま使用します。
- 油揚げは1か所切り目を入れて開き、熱湯でゆでて油抜きをします。
- 5.に半分に切った餅を詰めます。
- かんぴょうは塩(分量外)もみし、透き通るまでゆでます。
- 6.の口を、7.のかんぴょうでしばります(つまようじでも良い)。
- ゆで卵の殻をむきます。
- 昆布はたっぷりの水に浸け、しばらく置きます(浸け汁は使用します)。
- 牛すじはゆでてから切り、串に刺します。
- タコは長めに切り、串に刺します。
- 10.の昆布汁を煮立てから花かつおを入れ、漉して出汁を取ります。
- 広い浅めの鍋に餅きんちゃく以外の具を並べ、結び昆布も入れてたっぷりの出汁を入れます。
- 14.が煮立ったら(A)を加え、30~60分程煮ます。
- 味が良くしみたら皿に盛り、ゆでたにんじんとマスタードを添えます。
味噌おでん
愛知県の食に欠かせないのが、八丁味噌に代表される豆味噌(赤味噌)です。
大豆を原料に麹菌を繁殖させて大豆の麹をつくり、この豆麹を使って長期間、発酵・熟成させたものが豆味噌です。最低でも1年、長いと2年から3年も熟成させて作られる豆味噌は、「濃厚なコクと酸味」があります。
そんな豆味噌を使った愛知県独特のおでんが「味噌おでん」です。「味噌おでん」は、具材が入った土鍋の真ん中に味噌壺を置き、具材を味噌ダレにつけて食べるというものですが、近年では飲食店などで豆味噌仕立てのだし汁に具材を入れて煮こむ「味噌おでん」が増えてきています。
今回は、赤みその煮込みおでんを紹介します。
赤みそ煮込みおでん~7種の具で~

| 材料 | 4人分 | |
|---|---|---|
| 国産牛すじ肉 | 200g | |
| 里芋(中~大) | 4コ(400g) | |
| 大根(輪切り) | 500g | |
| 卵(ゆでる) | 4コ | |
| ちくわ | 4本 | |
| 厚揚げ(1枚160g位) | 2枚 | |
| 玉こんにゃく | 12粒 | |
| A | 八丁みそ | 200g |
| 砂糖 | 100g | |
| みりん | 大さじ4 | |
| 酒 | 大さじ4 | |
| しょうゆ | 大さじ2 | |
| 混合出汁 | 1400ml | |
| にんじん(もみじ形・スライス) | 4枚 | |
| フレンチマスタード(お好みで) | 適量 | |
作り方
- 牛すじは適当な大きさに切り、ゆっくりとゆでます(圧力鍋の場合は8分程ゆでます)。冷めてから串に刺します。
- 里芋は皮をむき、1人2コ当てに切ります。
- 大根は1人1切れ当てとし、裏側に十文字の切り込みを入れて米のとぎ汁で30分程ゆでます(厚力鍋可)。
- 卵は穴を開けて沸騰した湯に入れて、12分程ゆでて殻をむきます。
- ちくわは1本を斜め2つに切ります。厚揚げは熱湯で5分程ゆでてから、1丁を三角形に半分に切ります。
- 玉こんにゃくは塩もみしてゆでます。1本の竹串に3コずつ刺します。
- ボウルに(A)を入れてよく混ぜ、分量の出汁でのばします。
- 大きめの鍋に具材を並べて7.を注ぎ、じっくりと煮ます。小鉢に取り分け、ゆでたにんじんを添えます。お好みでマスタードを添えます。
※竹串は15cmの長さのものを使いました

