文化講座
第6回:北陸(新潟・富山・石川・福井)・信州(長野)
前シリーズでは「発酵食品の魅力にせまる」と題し、代表的な発酵食品を毎月順番に取り上げ、その特徴や健康効果、おすすめの料理をご紹介しました。今シリーズでは、筆者が全国各地を食べ歩いて研究した郷土の味、その土地の人々から愛されてきた逸品を、作りやすいレシピにしてご紹介しています。
第6回目の今月は、北陸「新潟・富山・石川・福井」・信州「長野」です。
1.北陸・信州地方
新潟県
- 面積:12,583.83km2
- 人口:2,330,142人(2013年11月現在)
- 県庁所在地:新潟市
石川県
- 面積:4,185.67km2
- 人口:1,158,995人(2013年11月現在)
- 県庁所在地:金沢市
長野県
- 面積:13,562.23km2
- 人口:2,119,714人(2013年11月現在)
- 県庁所在地:長野市
富山県
- 面積:4,247.61km2
- 人口:1,075,905人(2013年11月現在)
- 県庁所在地:富山市
福井県
- 面積:4,189.88km2
- 人口:794,320人(2013年11月現在)
- 県庁所在地:福井市
2.北陸・信州地方の食文化
北陸地方は日本海に面している事から、魚介類が多く獲れ、海産物を使った名物料理が多くあります。
福井県の「越前がに」・富山県の「マス寿司」などが、特に知られています。
カビなどの活動に適した湿度・冬の適度に低い気温や降雪から、発酵食品を作り出す為に適した良い環境でもあり、石川県の「ふぐの糠漬け」はとりわけ有名です。
猛毒を持つふぐの卵巣を使用し、塩と糠を使ってじっくり時間をかけた化学変化は毒を無毒化するとともに旨味を引き出します。
信州地方と言えば「そば」を思い浮かべるほど、長野県とそばは縁深いことで知られています。
他にも山菜やハチの子、クマやシカの肉など山の珍しいものがあったり、内陸盆地の気候がフルーツを育てるのにぴったりのため、果実をふんだんに味わうことが出来ます。
豊かな海の幸・山の幸に恵まれた北陸・信州地方の食を紹介します。
3.北陸・信州地方の名産品と郷土料理
北陸・信州地方には数多くの名産品がありますが、ここではその一部を紹介します。
☆新潟県
料亭「鍋茶屋」
弘化3年(1846年)に、高橋谷三郎氏が店を開いたと伝えられています。
鍋茶屋のしるしとなっている「亀甲型」は、初代が提案した「すっぽん料理」に由来しています。
「すっぽん鍋」を売り物とする店としてスタートしたのです。

鍋茶屋(新潟県新潟市中央区東堀通8-1420)の玄関での筆者(1991年4月)
新潟加島屋(塩干物屋)
安政2年(1855年)、信濃川や阿賀野川で獲れる鮭や鱒などの塩干物を商う店として創業しました。
昔ながらの手作りの味を大切にし、素材を厳選し、新潟の風土や食文化の中から生まれ、受継がれてきた郷土の味を作り続けています。
鮭や筋子、鱈の子、ホタテなど、自然の恵みを一つ一つ人の手で丁寧に仕上げた味わいです。

新潟加島屋(新潟県新潟市)の店先での筆者(1991年4月)
かんずり
「かんずり」とは元々新潟県妙高市近辺に伝わる家庭の調味料で、「唐辛子漬け」の事を指します。
製造過程における大きな特徴は、「雪さらし」と「三年熟成」です。
唐辛子の雪さらしは、妙高の冬の風物詩ともなっています。
味・品質ともに、"完成された極上の調味料"と言えます。

写真:かんずり(製造元:かんずり、住所:新潟県妙高市西条438-1)
☆富山県
料亭「くれは山荘」
富山市郊外の呉羽山山麓にある料亭。
八尾の山菜を中心に、地元の旬の食材を使った懐石料理がいただけます。

くれは山荘(富山県富山市西金屋67-7)の玄関前での筆者
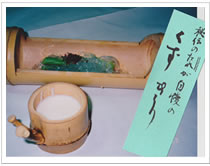
秘伝のタレが自慢のくず切り(1991年4月)
細工蒲鉾
鯛や水引などの形の蒲鉾。
結婚式の引出物などとして使われ、本格的なものは鯛型で実物大程の大きさがあります。

富山県から取り寄せた細工蒲鉾・おめで鯛
☆石川県
~金沢市~
料亭「つば甚」
金沢市内の名料亭です。
代々加賀藩のお抱えつば師だった、四代目甚兵衛が宝暦2年(1752年)に現在の場所で創業しました。
伊藤博文や芥川龍之介などの著名人が、つば甚の料理を食べに金沢を訪れました。

つば甚(石川県金沢市寺町5-1-8)で料理(にらみ鯛・俵蓮餅・俵唐蒸しなど)を前にした筆者

つば甚で食べた加賀名物・鴨治部煮(2006年11月)
近江町市場
江戸時代に近江商人が移り住み、50軒ほどの魚市場として開設されました。300年に亘って活気に満ち、現在は海の幸と山の幸の店がそれぞれ並び、約170店舗あります。

近江町市場(石川県金沢市上近江町50)での筆者

市場内の「いきいき亭」で食べた「特製北陸丼」(2012年6月)
加賀野菜
昭和20年以前から石川県金沢市で生産され、金沢市農産物ブランド協会が認定した野菜。
現在15品目あります。
- 加賀太きゅうり:瓜のように太いきゅうり。
普通のきゅうりの5本分程度の量があり、皮をむいて種を取り出して食べます。 - 金時草(きんじそう):葉の裏の、金時芋や金時豆に似た赤紫色から連想して名付けられました。
茹でるとぬめりが出て、酢の物などで食べられます。

金時草

加賀太きゅうり

猩猩(しょうじょう・石川県金沢市香林坊2-12-15割烹むら井ビル1F)で食べた加賀太きゅうりと金時草とカニの酢の物(2012年6月)
香箱ガニ
香箱ガニとは、北陸地方で捕れるメスのずわい蟹で、オスより小ぶりですが中には茶色い卵とオレンジのみそがたっぷり詰まっており、旨みが凝縮されています。

黒百合(金沢駅内・石川県金沢市広岡町ロ-1 金沢百番街内あじわい館)で食べた香箱ガニ

輪島直送タグ付きずわい蟹と香箱ガニ(2013年12月)
~輪島市~
輪島朝市
地元のとれたての魚や海藻などの海産物・野菜・輪島塗の民芸品などが並ぶ輪島朝市は、千年以上も前から続いています。
もとは鳳至比古神社の例祭から始まったと言われています。
ほおかむり姿のおばさんたちが元気のいい声を張り上げ、商品を売る様子に元気をもらえます。

輪島の朝市通り(石川県輪島市河井町)の入り口での筆者

ほおかむり姿のおばさんがブリを捌きながら売る様子(2013年12月)
丸柚餅子(ゆべし)
柚子のヘタを取って中を出し、果肉と米粉、砂糖を練ったものを詰めてフタをし、何回か蒸して日光に干したものです。
応仁の乱を避けた京の職人が伝えたといわれ、源平時代からの保存食や携帯食とされる、伝統の香り豊かな菓子です。

良澤本店(石川県輪島市鳳至町上町29)の丸ゆべし

柚餅子総本家 中浦屋・朝市店(石川県輪島市河井町1部103-3)の店内での筆者(2013年12月)
いしるの貝鍋
いしるとは、石川県能登地方で作られるイカや魚を原料にしたしょうゆのことです。

まつおか(石川県輪島市河井町1部31-1)で食べた「いしるの貝鍋」(2013年12月)
☆福井県
越前おろしそば
主に福井県嶺北地方で食されるそばです。
そばにおろし大根を載せて出し汁をかけたり(ぶっかけ)、おろし大根に出し汁を加えて付けつゆにして食べる(つけそば)など、おろし大根を利用する事から、「おろしそば」と呼ばれています。
◇そば処「聴琴亭」
鯖江(5万石)七代藩主、間部詮勝(まなべあきかつ)公から店名を取った聴琴亭(ちょうきんてい)は、庄屋(安政年間)であった旧家の名残をそのままにとどめています。
600坪の広大な敷地に純和風総ケヤキ造りの建物、落ち着いた庭園を楽しみながら、聴琴亭独特の伝統料理と純手作りの十割蕎麦とうどんの味が殿様気分で楽しめます。

聴琴亭(福井県鯖江市新庄町63-44)の玄関前での筆者

聴琴亭名物「聴琴そば」(2010年4月)
他にも「けんぞう蕎麦」「御清水庵」「かめや」などの店で、蕎麦が食べられます。

けんぞう蕎麦(福井県吉田郡永平寺町松岡春日3-26)の辛みそば(2012年6月)
サバ街道
サバ街道は若狭国などの小浜藩領内(おおむね現在の嶺南に該当)と、京都を結ぶ街道の総称です。
主に魚介類を京都へ運搬するための物流ルートでしたが、その中でも特にサバが多かった事から、近年に至り名付けられました。
◇生簀割烹・雅
四季折々の若狭小浜の新鮮な素材の数々、その旬を選び集めた、こだわりの職人の技が冴える店です。
「浜焼き鯖」など、小浜湾のとれたての魚も提供しています。

生簀割烹・雅(福井県小浜市香取107)で食べた浜焼き鯖

サバ寿司(2009年5月)
他にも「田村長」で、鯖料理をいただきました。
☆長野県
信州そば
信州そばは、長野県で作られるそばの総称です。
一般的に食べられている「そば切り(細く切ってから食べる)」は信州から始まったと言われており、それ以前は団子状の「そばがき」や、囲炉裏の灰で焼く「お焼き」として食べるのが一般的でした。
そばは短い期間で収穫でき、痩せ地や高冷地でも栽培に適したことから、かつては救荒作物として普及しました。しかしそば切りはハレの日のごちそうとして食べられ、江戸時代中期以降、江戸の庶民も食べるようになったのです。
◇くるまや本店
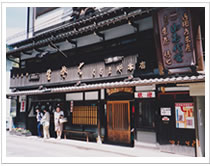
くるまや本店(長野県木曽郡木曽町福島5367-2)の店先での筆者

山菜天ぷら・とろろ付きそば(1991年4月)
他にも「そば処もとき」「そば処こうの」でも食べられます。
フルーツ狩り
信州はフルーツが美味しく育つのにぴったりの気候風土で、各農園でフルーツ狩りが楽しめます。
果樹が生長する時期に雨が少なく日照時間が長いため、余分な樹の成長が抑えられて果実が十分な日光を浴びてじっくりと育ちます。
内陸盆地で、昼夜の温度差が大きいため、果実のうまみが増します。

JA中野市農産物産館オランチェ(長野県中野市草間1543-5)でさくらんぼ狩り中の筆者(2010年5月)

榎本農園(長野県下伊那郡松川町大島2979-4)でりんご狩り中の筆者(2012年11月)
善光寺の宿坊・兄部坊(このこんぼう)
善光寺は「一生に一度お参りすれば極楽浄土」とされ、宗派によらず、老若男女すべてに平等に救済を説くことから広く信仰されています。
宿坊の兄部坊では、信州の旬の食材を活かした精進料理が食べられます。

信州善光寺 宿坊・兄部坊(長野県長野市元善町463)の入り口で兄部坊の執事と筆者

兄部坊で食べた精進料理「車麩の含め煮(豚の角煮もどき)」(2010年6月)
駒ヶ根ソースかつ丼
昭和の初め頃から駒ヶ根市内で提供されていた丼で、駒ヶ根では「かつ丼」というと「卵でとじたかつ丼」ではなく、「ソースかつ丼」が一般的でした。
発祥は駒ヶ根駅構内あたりのカフェを営んでいた、「喜楽(現在のきらく)」の初代が食道楽で、熱々揚げたてのトンカツにソースをかけ、冷たい歯触りのキャベツとの食感が良いと、こだわって作ったと言われています。
◇きらく

きらく(長野県駒ヶ根市赤穂3145)の店先での筆者

きらくのソースかつ丼(2011年11月)
◇明治亭

明治亭(長野県駒ヶ根市赤穂898-6)の店先での筆者

明治亭のソースかつ丼(2012年11月)
他にも「きよし」「ガロ」でも食べられます。
4.北陸・信州の郷土料理レシピ

かつおだしのきいた手作りつゆのカニ鍋
| 材料(4人分) | 分量 |
| 白菜 | 300g |
| 三つ葉 | 大1束 |
| えのき茸 | 200g |
| 生しいたけ | 4枚 |
| 生巻き湯葉 | 1本(35cm) |
| 生ズワイガニ(カニすき用・冷凍・殻付き) | 400~500g |
| A | |
| かつおだし | 1000ml |
| 酒 | 50ml |
| 薄口しょうゆ | 大さじ1強 |
| みりん | 大さじ1・1/2 |
| 塩 | 小さじ1 |
作り方
- 白菜は茹でて水に取って冷まします。まきすの上に葉先を並べ、その上に白い軸の部分をのせ、まきすでしっかりと巻き、5cm長さに切ります。
- 三つ葉は軸を切って2等分、えのき茸は石突きを落とし、サッと洗って手でほぐし、しいたけは傘に飾り切りをします。
- 湯葉は8等分に切ります。
- 鍋に(A)を入れ、1.~3.とカニを入れて火にかけます。
- 4.の食材に火が通ったら、器に盛ります。
※残った煮汁から具をきれいにすくい取り、茶碗一杯分のご飯(水で洗わない)を入れて煮ます。
ご飯が軟らかくなったら、火を止めて溶いた卵3コ分を入れ、余熱でとろとろになるまで火を通すと、「とろとろ卵おじや」が出来上がります。

美味しさの決め手はいちごジャム入りのソース
| 材料(2人分) | 分量 |
| 豚ひれ肉(塊) | 200~250g |
| A | |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 適宜 |
| 卵 | 1/2コ |
| 水 | 大さじ1/2 |
| 生パン粉 | 1カップ強 |
| 揚げ油 | 適宜 |
| キャベツ | 2枚(140g) |
| B | |
| ウスターソース | 大さじ2弱 |
| トマトケチャップ | 大さじ2弱 |
| 酒 | 大さじ2弱 |
| 水 | 大さじ2弱 |
| しょうゆ | 大さじ1/2 |
| いちごジャム | 大さじ1 |
| ご飯 | 600g |
作り方
- 豚肉は1.5mmの厚さに切り、(A)で下味をつけます。
- 1.の両面に小麦粉をはたき、溶き卵(卵をかきまぜて水を加えたもの)をつけ、パン粉をまぶしつけます。
- 揚げ油を熱し、170度くらいで2~3分間揚げ、裏返して更に1~2分間揚げます。
- キャベツはせん切りにし、氷水にさらしてパリッとさせます。
- (B)を鍋に入れ、少し煮つめます。
- 器にご飯をもり、よく水気を切った4.をのせます。
- 3.を5.にサッとくぐらせ、6.の上にのせます。

