文化講座
第12回:沖縄県
前シリーズでは「発酵食品の魅力にせまる」と題し、代表的な発酵食品を毎月順番に取り上げ、その特徴や健康効果、おすすめの料理をご紹介しました。今シリーズでは、筆者が全国各地を食べ歩いて研究した郷土の味、その土地の人々から愛されてきた逸品を、作りやすいレシピにしてご紹介しています。
第12回目(シリーズ最終回)の今月は、沖縄県です。
1.沖縄県

沖縄で守り神とされている「シーサー」の置物(2014年5月)
- 面積:2,276.72km2
- 人口:1,419,893人(2014年2月現在)
- 県庁所在地:那覇市
2.沖縄県の食文化
沖縄は亜熱帯の気候であること、歴史的に日中両国の文化の影響を受けて、独自の食文化が発達してきました。
その食文化は、かつて首里を中心に発達した琉球王朝の「宮廷料理」と、庶民の間で発達した「庶民料理」の2つに大きく分けられます。
日中両国の国賓・官吏を接待する必要から両国の料理技術を積極的に取り入れ、さらに独自の工夫をした、「宮廷料理」と、台風やかんばつという厳しい気候条件の中、食品保存に工夫をこらし、食生活に知恵を集約したものが「庶民料理」として発達したのです。
沖縄料理の特色としては、豚肉料理が多いことが上げられます。
沖縄料理は「豚に始まり豚に終わる」と言われるほど、頭から足の先、血や内臓に至るまで余す所なく、料理に使用しています。
その他にもナーベーラー(へちま)・ゴーヤーなどの夏野菜、バナナ・パッションフルーツ・ドラゴンフルーツ等の亜熱帯の果物も採れます。
沖縄県は独自の料理が楽しめる、魅力あふれる島です。
3.沖縄県の名産品と郷土料理
沖縄県には数多くの名産品がありますが、ここではその一部を紹介します。
琉球料理「美栄(みえ)」
沖縄の伝統料理「東道盆(とぅだーぶん)」が食べられる、老舗料亭です。
東道盆とは、宮廷料理でオードブルに相当するもので、細工が見事な六角形の漆器で出されます。
ポーポー(小麦粉を薄く焼いてクレープ状に巻いたもの)や昆布巻き、グルクンと呼ばれる赤い魚を使ったかまぼこなどの前菜が盛られています。
ナカミーの吸い物の「ナカミー」とは、豚の腸や胃などの内臓のことで、しっかりと下処理されたナカミーはクセがなく、上品な吸い物に仕上がっていました。
「豚は鳴き声以外はすべて食べる」という沖縄の食文化らしく、ミミガー(豚の耳の皮)の和え物、ミヌダル(豚肉に黒ゴマをまぶして蒸したもの)、ラフテー(豚の角煮)などの豚肉料理が続きます。
他にもジーマーミー(落花生)豆腐、いもくずアンダーギー、クーブイリチー(昆布の炒め物)などの沖縄料理が楽しめます。

琉球料理「美栄」(那覇市久茂地1-8-8)
東道盆7品盛りを前にした筆者

ナカミーの吸い物

ミミガーの和え物(2014年5月)

沖縄名物の「ラフテー」

いもくずアンダーギー(アンダーギーとは沖縄の天ぷらのことで、衣に塩味がついているのでそのまま食べられます)(2014年5月)
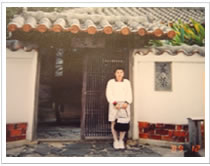
1989年12月にも同店を訪れています
店前での筆者
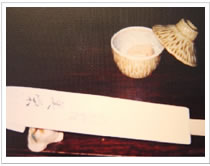
自家製・豆腐羹(豆腐を発酵させたもの)
八重山料理「潭亭(たんてい)」
首里城近くにある、八重山地方の伝統料理が楽しめる店です。
石垣島より取り寄せた食材を店主・宮城礼子さんが調理しており、女性らしい繊細な味付けと美しい盛りつけが特徴的です。

八重山料理「潭亭」(那覇市首里赤平町2-40-1)
店内での筆者

沖縄名物の「ジーマーミー豆腐(落花生で作った豆腐)」

八重山流「彩飯(白飯の上に野菜や肉、卵を彩りよく盛り、だし汁をかけた、琉球王朝料理として知られるお茶漬け)」
ゆうなんぎい
那覇市の中心地・国際通り近くにある、沖縄料理が楽しめる店です。
海ぶどうやスヌイ(もずくの酢の物)、スルルの(きびなご)唐揚げ、ミミガー(豚の耳)、島らっきょう、フーチャンプルー(麩の炒め物)やラフテー、沖縄そばなど、沖縄の定番料理が手軽に楽しめます。

ゆうなんぎい(那覇市久茂地3-3-3)
店先での筆者

沖縄で作られるオリオンビールを飲む筆者(2014年5月)

海ぶどう(写真左・食感や外観から「緑のキャビア」と呼ばれる海藻)と沖縄もずく

島らっきょう(一般的ならっきょうより小粒で細く、独特の香りや辛味はやみつきになります)(2014年5月)
第一牧志公設市場
那覇市の中心地にあり、那覇市民の台所として60年以上親しまれ、現在は観光客も多く訪れる観光地になっています。
市場は2階建てになっており、1階には肉・魚・惣菜店などが並び、鮮魚店で購入した魚介類は、すぐに2階の食堂で調理して食べることが出来ます。
チラガー(豚の顔肉)やカラフルな魚など、沖縄らしい食材が所狭しと並んでいます。
市場の周りは市場本通り商店街になっており、土産物店や乾物屋などが並んでいます。
その場でさとうきびを絞って飲ませてくれる店、ブルーシール(アイスクリーム店)、フルーツショップもあり、多くの人で賑わっています。

「第一牧志公設市場」(那覇市松尾2-10-1)
市場入口での筆者

しぼりたてのさとうきびジュースが飲める店での筆者

市場の魚屋で売られていた新鮮な魚(2014年5月)

2004年3月にも同市場を訪れています
しぼりたてさとうきびジュースの店

ヘチマや紅芋など沖縄らしい食材が並ぶ様子

沖縄そば(そば粉ではなく、小麦粉をかん水を使って打った中華麺に近い麺に、三枚肉をトッピングした沖縄の麺料理)
乾物屋「松本商店」
かつお節の塊が並び、その場で削って真空パックに詰めてくれます。
沖縄県はかつお節の消費量は全国1位で、全国平均の約7倍です。
かつお節の他にもクーブイリチー用の刻み昆布や、太もずく、かちり(片口いわし)などが売られています。

乾物屋「松本商店」(那覇市松尾2-11-13)
かつお節の干物を手に持った筆者(2014年5月)
スーパーの乾物コーナーにも多くの花かつおが並びます。

スーパーマーケットで花かつおを見る筆者(2014年5月)
道の駅「いとまん」
日本最南端にある糸満市の道の駅です。
ファーマーズマーケットとお魚センター、物産センターの建物が同じ敷地内にあり、沖縄で最大の道の駅です。
採れたての新鮮な野菜や果実、水揚げされたばかりの魚介類を購入できます。
フーチバー(ヨモギ)や島らっきょう、島にんじん、島バナナ、パッションフルーツなど、沖縄ならではの食材に歓喜しながら買物しました。

道の駅「いとまん」(糸満市西崎4-19-1)
JAファーマーズ内での筆者

お魚センターで購入した、新鮮なマグロの刺身とうに(2014年5月)
首里城
首里城は沖縄がかつて琉球王国として栄えていた頃、政治・外交・文化の中心でした。
琉球王国は1429年から1879年までにわたり存在した王政の国で、中国や日本、東南アジア等との交易から様々な交物がもたらされ、独自の文化が花開き、その中心が首里城だったのです。
2000年12月に、日本では11番目に世界遺産に登録されました。

首里城(那覇市首里金城町1-2)
守礼の門前で沖縄民族衣装「琉装」を着た筆者

世界遺産認定記念碑前での筆者(2014年5月)

2004年3月にも首里城を訪れています
守礼の門前での筆者
甘味処「干日」
ぜんざい専門の老舗です。
器の下には金時豆のぜんざい、上にはパウダー状の氷が高さ25㎝ほどに盛られています。
あまりの大きさに驚きますが、氷がふわふわしているので、さらっと食べることが出来ます。
通常「ぜんざい」と聞くと小豆で作った温かい汁粉を思い浮かべる人が多いと思いますが、沖縄では「ぜんざい」は金時豆を煮たものに、ふわふわのかき氷をのせたものが一般的です。

甘味処「干日」(那覇市久米1-7-14)
ぜんざいかき氷(2014年5月)
御菓子御殿
元祖紅いもタルトのお店です。
読谷村の村おこしとして沖縄県特産の紅いもでお菓子を作ったところ、銘菓として知られるようになりました。
国際通りにあるこの店では、出来たての紅いもタルトと紅いもを使ったケーキなどを食べることが出来ます。

御菓子御殿・国際通り松尾店(那覇市松尾1-2-5)
紫芋タルトのモニュメントと筆者

御菓子御殿内で購入した生紅いもタルトやケーキ(2014年5月)
ぶくぶく茶
ぶくぶく茶は、煎ったお米と玄米をミネラル豊富で硬度の高い沖縄の水を使って煮出した煎米湯に、さんぴん茶などを合わせ、それを大きな茶筅で泡立てて作ります。
明治から昭和の初期まで那覇の一部の家庭で好まれ、お祝いの席(結婚式、新築祝い、出産祝いなど)で主に飲まれていました。

ぶくぶく茶
サーターアンダギー(沖縄ドーナツ)
沖縄を代表するお菓子で、サーターは「砂糖」、アンダギーは「揚げ物」を意味します。 砂糖、卵、小麦粉にベーキングパウダーを混ぜ、手ですくって軽く握って油の中に入れて揚げます。
表面が割れて、お花のように開いたら成功です。

サーターアンダギー
4.沖縄県の郷土料理レシピ

「チャンプルー」とは、沖縄の方言で「混ぜこぜにした」という意味の炒め物
| 材料(2人分) | 分量 |
| ゴーヤー | 1/2本分(150g) |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| 豆腐(木綿) | 1/2丁 |
| 豚肩ロース肉(薄切り) | 70g |
| サラダ油 | 大さじ1・1/2 |
| A | |
| しょうゆ | 大さじ1弱 |
| 酒 | 大さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 卵 | 1コ |
| 花かつお | 適宜 |
作り方
- ゴーヤーは縦半分に切って種と白いワタを取り除き、3~4mmの薄切りにします。苦味を抜くため塩でもんだ後、水洗いして絞ります。
- 豆腐は4等分にし、10分間ほど軽く重しをして水気をきります。
- 豚肉は一口大に切ります。
- フライパンに油大さじ1を入れ、強火にします。そこへ豆腐を手でくずしながら加え、焼き色がつくまでしっかりと焼きつけてから、いったん取り出します。
- フライパンに油大さじ1/2を足して豚肉を炒め、色が変わったらゴーヤーを加えてしっかりと炒めます。
- 5.に(A)を入れてサッとからめ、4.を戻し入れて溶き卵を加え、さっと炒めます。
- 器に盛って花かつおをのせます。

クーブは「昆布」、イリチーは「炒め物」を意味します
| 材料(4~6人分) | 分量 |
| 豚三枚肉(塊) | 100g |
| 水 | 4カップ |
| かつお節 | 10g |
| 切り昆布 | 50g |
| 干ししいたけ | 4枚 |
| 揚げはんぺん | 80g |
| にんじん | 1/3本(60g) |
| サラダ油 | 大さじ1・1/2 |
| 豚とかつおの茹で汁 | 300ml |
| しいたけの戻し汁 | 100ml |
| A | |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| 酒 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ2 |
作り方
- 豚肉を鍋の大きさに合わせて切り、水から茹でて沸騰してから10分間を目安にし、豚肉に火が通るまで茹でます(茹で汁は後で使用します)。
- 1.の茹で汁を煮立て、かつお節を入れて2~3分間煮出して漉します。
- 切り昆布と干ししいたけはそれぞれ水で洗い、たっぷりの水に浸して戻します。
- 1.の豚肉と揚げはんぺんは1cm幅の短冊切り、にんじんは皮をむいてせん切りにします。
- フライパンに油を敷き、にんじんと3.のしいたけをスライスして炒め、戻した昆布を加えて更に炒めます。
- 5.に2.のだし汁としいたけの戻し汁、4.のはんぺんと豚肉を加え(A)で調味して汁気が少なくなるまで炒り煮にします。
- 器に盛ります。
皆様の益々のご健康をお祈りし、今シリーズを終わらせて頂きます。
次シリーズでは、「愛する人に作りたいスイーツレシピ」というテーマで、お菓子の歴史やその名前の由来、誕生秘話などを取り入れながら、家庭で作りやすいスイーツレシピを毎月2点ずつご紹介する予定です。
引き続きのご愛読をお願い申し上げます。

