文化講座
第6回 大韓民国
前シリーズでは、気軽に作れておしゃれなもてなしレシピ、盛り付けのコツ、器の選び方、テーブルセッティングなどをご紹介しました。
シリーズ19回目の今シリーズでは、「世界のとっておきグルメ」というテーマで、世界各国を食べ歩いて料理研究に余念のない伊藤華づ枝が、食べて感動した料理や店をご紹介しております。
家庭で作れる現地レシピも併せてご紹介します。
第6回目の今月は、「大韓民国」です。
大韓民国

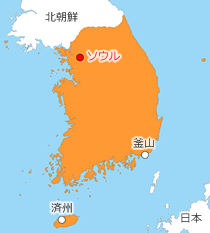
韓国は朝鮮半島の南部にあり、東アジアの共和制国家です。
平野部が少なく、山地が多い国です。
ソウル首都圏に人口が最も集中しており、全人口の約半数が居住しています。
<基本情報>
■首都:ソウル
■人口:5,150万人(2015年)
■面積:10万km2(日本の約4分の1)
■宗教:仏教・プロテスタント・カトリックなど
■言語:韓国語
■時差:韓国と日本の時差はありません
■通貨:ウォン(W) W1=約¥0.1(2017年9月現在)
韓国の民族衣装
女性はチマチョゴリを着ます。
チマチョゴリとは、男女共通の上着「チョゴリ」と、胸からくるぶしくらいまでの長さがある巻きスカート「チマ」のことです。


伊藤華づ枝のチマチョゴリ姿
韓国の食事情
ご飯を主食とし、おかずと汁物と共に食べます。
海に囲まれた国のため、魚介類や海藻をよく食べます。
キムチなどの発酵文化が発達しており、合わせ調味料「ヤンニョム(薬念)」が生まれました。
ヤンニョム(薬念)とは
古来より伝わる五味(甘・辛・苦・酸・塩)と五色(白・赤・黒・黄・緑)を取り込んだ、合わせ調味料のことです。
薬味のねぎ・しょうが・にんにく・ごま・唐辛子・松の実・干しエビ・梨・りんご・柿などと、調味料のコチュジャン・みそ・しょうゆ(魚醤)・ごま油・アミの塩辛などを混ぜ合わせます。
「薬念」とは、「食が薬になる」という医食同源の思想に基づいています。


韓国といえば「キムチ」
キムチとは、白菜などの野菜を塩漬けし、唐辛子・魚介の塩辛・にんにくなどを使用した漬け物のことです。
もともとは、朝鮮半島の冬の保存食として野菜を塩漬けしていたことが始まりです。
キムチに使われる唐辛子は、16世紀に豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に日本から朝鮮半島に持ち込み、18世紀末頃からキムチ作りに使われるようになりました。
それまでは「ムルキムチ(水キムチ)」が主流で、山椒が辛味として使われていました。
ソウルの仁寺洞にある「ミュージックキムチ館」でキムチの伝統や歴史を学びました。
韓国では冬にキムチを漬け、ツボ(キムジャンドク)に入れて土に埋めたキムチの味が究極の味と認められています。低温で長期間熟成することで、最高の味が出せると考えられています。
2016年10月

さまざまなキムチの展示

キムチを漬けるツボ

ソウルで習った白菜キムチ

カクテキ
(大根キムチ)

オイキムチ
(きゅうりのキムチ)

伊藤華づ枝作
白菜キムチ
韓国では、キムチ=オモニ(お母さん)を意味し、キムジャンと呼ばれるキムチ作りが1年のうちで最も重要な行事のひとつです。 かつては、キムジャン休暇やキムジャンボーナスを出す企業もあったほどです。
食べごろを逃して酸っぱくなってしまったキムチは、炒め物や煮物、チゲ(鍋料理)に活用します。
食事に使う道具

スッカラ(さじ)
チョッカラ(箸)
スジョを使って、食事をします。
スジョとは、スッカラ(さじ)とチョッカラ(箸)のことをいいます。
主に使うのは、スッカラ(さじ)で、チョッカラ(箸)はおかずをつまむ時にだけ使います。
食器は持ち上げずに置いたまま、食事をします。
韓国宮廷料理
李朝時代に王様が食べていた料理で、各地方から献上された最高の食材を使った料理です。
食材本来の味を生かした素朴な味で、彩りを考えた美しい盛り付けが特徴です。
韓国の慣用句で「机の脚が折れるほどの料理」という言葉があり、これは料理の品数が多ければ多いほど良いという意味です。
宮廷料理のフルコースでは、料理の数が30種類を超えるものもあります。


韓国宮廷料理「荘園」
ソウル市内にある店で、テーブルいっぱいに並ぶ宮廷料理が食べられます。
1980年頃
宮廷料理を家庭的にアレンジした「韓定食」は、気軽に食べられます。
韓定食では、ご飯とチゲ(小さな鍋物)に、10~20種類のおかずや、キムチなどの付け合わせが出されるのが一般的です。


クジョルパン

竹筒ご飯
韓定食「紫霞門」
錦糸卵やナムルなどを、薄いクレープで包み、タレをつけて食べます。本物のクジョルパン(九節板)は、8種類の具材とクレープを9つに仕切られた器に盛ります。
2009年10月
韓国焼肉
骨つきカルビやロース肉などを網で焼き、ハサミで切ってタレをつけ、サンチュやエゴマの葉で巻いて食べます。
ソウルで食べた焼肉
2009年10月・2016年10月



石焼ビビンバ
専用の石鍋にご飯とナムル、肉、卵などを入れてよくかき混ぜて食べる料理のこと。
ご飯の上に盛られる具は基本5種類とされています。
「ピビン」が"混ぜ"、「パプ」が"ご飯"を意味し、ビビンバと呼ばれるようになりました。


石焼ビビンバ発祥の店と言われている「全州中央会館」
1990年・2009年・2016年


この店のマッコリ(どぶろく)は絶品です。
マッコリとは、朝鮮半島の伝統酒で、米を主原料にするアルコール発酵飲料。
参鶏湯(サムゲタン)
ひな鶏の中に米や朝鮮人参、なつめ、栗、にんにく、しょうがなどを詰めて鶏が柔らかくなるまで、じっくりと煮込んだ薬膳スープ。

ソウルの「全州会館」で食べた参鶏湯
2016年10月

伊藤華づ枝作
参鶏湯
パジョン(チヂミ)
韓国風のお好み焼き。少量の油でパリッと仕上げるのが、ポイントです。

ソウルの「全州会館」で食べた海鮮チヂミ
2016年10月


伊藤華づ枝作
牛肉とねぎのチヂミ
ミシュラン星つきレストラン
2016年から韓国・ソウルのミシュランガイドが発売されました。
3つ星レストランの「羅宴(ラヨン)」に行きました。

3つ星レストラン「羅宴」
2016年10月

栗のスープ

鮑塩混ぜ釜飯
韓国での買い物
市場


市場の様子
1990年

南大門市場の様子
2009年10月
もち菓子
韓国の伝統菓子で、はちみつや松の実、なつめ、豆などが入ったもち菓子が人気です。


青磁
青磁釉を施した磁器で、透明感のある青緑色が特徴です。



※もちもちとした食感が特徴の韓国春雨(さつまいもでんぷん)と、牛肉や野菜を炒めたもの
| 材料 | 4人分 |
| 韓国春雨(乾燥) | 200g |
| 牛肩ロース薄切り肉 | 200g |
| A | |
| しょうゆ | 大さじ4 |
| 酒 | 大さじ1・1/2 |
| 砂糖 | 大さじ2・1/2 |
| しょうが(すりおろし) | 小さじ1強 |
| にんにく(すりおろし) | 小さじ1/2強 |
| しめじ | 1パック(100g) |
| 赤パプリカ | 1/2コ(100g) |
| 万能ネギ | 80g |
| むきエビ | 8尾(90g) |
| 塩 | 少々 |
| 黒こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| B | |
| ごま油 | 大さじ1 |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| しょうが(せん切り) | 10g |
| 塩 | 少々 |
| 黒こしょう | 少々 |
| 白いりごま | 大さじ2 |
| 卵 | 2コ |
作り方
- 韓国春雨は沸騰した湯で、6~7分間茹でて戻します(食べて芯がなくなるくらい)。水に取ってもみ洗いし、水気を切ってざく切りにします。
- 牛肉は細切りにし、(A)をもみ込みます。
- しめじは石突きを取って2~3本ずつにほぐし、パプリカは種を取って細切り、万能ねぎは4cm長さに切ります。
- エビは背ワタを取り、塩と酒(分量外)でもみ洗いし、水で洗います。熱湯で茹で、ザルに上げて塩とこしょうで調味します。
- フライパンに油を敷き、4.のエビを焼き付けて一旦取り出します。
- 5.のフライパンに(B)を足し、しょうがをじんわりと炒め、しめじを加えて更に炒めます。
- 6.に2.を入れて炒め、肉の色が変わったら赤パプリカとねぎを入れ、1.を加えて炒め合せます。味をみて塩とこしょうで調味し、5.のエビを戻し入れて、ごまを混ぜます。
- 卵は薄焼きにし、せん切りにします。
- 器に7.を盛り、その上に8.の錦糸卵をのせます。

※きゅうりの食感が良く、切り込み部分に詰めた薬念が美味しい!
| 材料 | 作りやすい分量 |
| きゅうり | 500g(4本) |
| A | |
| 塩 | 大さじ3 |
| 水 | 600ml |
| <薬念>=ヤンニョム | |
| 大根 | 80g |
| 細ねぎ | 3~4本(10g) |
| にら | 3~4本(20g) |
| にんにく(すりおろし) | 大さじ1/2 |
| しょうが(すりおろし) | 小さじ1弱 |
| 梨(又はりんご) | 1/2コ(40g) |
| B | |
| 松の実 | 大さじ1(8g) |
| あみの塩辛 | 10g |
| ナンプラー(又はしょうゆ) | 大さじ1/2強 |
| 砂糖 | 大さじ1/2強 |
| 白ごま | 大さじ1/2強 |
| 粉唐辛子(粗め) | 大さじ2・1/2 |
| 塩 | 小さじ1 |
| C | |
| 上新粉 | 大さじ1 |
| 水 | 大さじ4 |
作り方
- きゅうりは1本を4等分の長さに切り、縦十文字に深く切り込みを入れます。
- 1.を(A)の塩分に20~40分間漬け込みます。
※ザルに上げて水で洗い流さないので注意する事!! - 2.がしんなりしたら、洗わずにしっかりと絞ります。
- 大根はせん切り、細ねぎとにらは3~4cmに切ります。にんにくとしょうがはすりおろします。梨(又はりんご)は皮をむいてすりおろします。
- 大きいボウルに(B)を合わせます。(C)を小鍋に入れて練って冷まします。ボウルに冷めた(C)と4.を入れ、ビニール手袋をしてよくもみこんで薬念を作ります。
- 3.の切り込み部分に薬念を挟み込み、味がなじむまでおきます。すぐに食べられますが、冷蔵庫に入れて翌日に食べると、とってもおいしいです。
※一晩冷蔵庫におくと味がなじんで良い
※冷蔵庫で保管して下さい
※(C)の上新粉は、小麦粉で代用しても良いでしょう
※写真奥は大根キムチ(カクテキ)です

