文化講座
第8回 お茶と共に楽しむお菓子 ~スコーンといちご大福~
前シリーズでは「日本全国食べ歩き~郷土の味を求めて~」と題し、筆者が全国各地を食べ歩いて研究した郷土の味、その土地の人々から愛されてきた逸品を、作りやすいレシピと共にご紹介しました。今シリーズでは、お菓子の歴史やその名前の由来、誕生秘話などを取り入れながら、家庭で作りやすいスイーツレシピを毎月2点ずつご紹介しています。
第8回目の今月は、「お茶と共に楽しむお菓子」、スコーンといちご大福です。
1.スコーン
スコーンとは、小麦粉・バター・牛乳・ベーキングパウダーやイーストなどを混ぜ合わせて焼いた、丸い小形のパン菓子(ビスケット)のことで、イギリス・スコットランド地方が発祥です。
スコーンの起源は、粗挽きの大麦粉をやわらかく練って鉄板で焼いた「バノック」というビスケットのようなお菓子と言われています。
19世紀半ばにベーキングパウダーやオーブンの普及により、現在のふっくらとした形に近づきました。

伊藤華づ枝作
スコーン
<名前の由来>
スコーンの名前の由来は2説あります。
1.スコットランド・バースにある「スコーン城」の歴代国王の戴冠式に使用されたイスの土台が、「運命の石」と呼ばれ、その名にあやかってつけられたという説。
石の形のように丸く焼くことが多いのは、そのためです。
神聖な石の形から、食べる時はナイフを使わずに縦に割ることもしません。
手で横半分に割って食べるのがマナーとされています。
2.スコットランドの古い言葉・ゲイル語の「Sgonn(ひと口大)」から来ているという説。
前者の説が有力視されています。
<スコーンとお茶>
イギリス発祥のアフタヌーンティーに、スコーンは欠かせません。
紅茶を飲みながら、スコーンにジャムやクロテッドクリーム、バターなどを添えていただきます。
アフタヌーンティーの発祥は1840年代のイギリスで、今から170年ほど前のことです。
ベッドフォード伯爵夫人のアンナ・マリアさんが、夕食までの空腹を満たすために、メイドにバター付きのパンと紅茶を運ばせたことに始まります。
今ではイギリスに限らず、世界各国の高級ホテルや日本でも気軽に楽しめるようになり、スコーンや小ぶりのケーキ、ティーサンドイッチと共に紅茶を楽しむ優雅なひとときとなっています。
<世界各国で伊藤華づ枝が体験したアフタヌーンティー>

ロンドン「ザ・レーンズボロ」でアフタヌーンティー

ロンドン「ブラウンズホテル」でハイティー(軽食やお酒も一緒に楽しむ夜のティータイム)

コッツウォルズ「マーメイド」でクリームティー(スコーンと紅茶を楽しむティータイム)

マレーシア「カルコサスリネガラ迎賓館」でアフタヌーンティー

シンガポール「ラッフルズホテル」でアフタヌーンティー

シンガポール「リッツカールトン」でアフタヌーンティー

香港「ザ・ペニンシュラホテル」でアフタヌーンティー

名古屋「マリオットアソシアホテル」でアフタヌーンティー
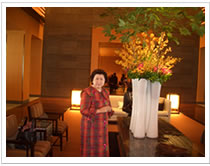
東京「マンダリンオリエンタルホテル」でアフタヌーンティー

スコーンに添えるクロテッドクリーム(デボンシャークリームとも言う)とは、「凝固したクリーム」という意味で、生クリームとバターの中間のようなもので、濃厚ながら爽やかな味わいが特徴です。
アメリカではスコーンを「ビスケット」と呼んでおり、ほぼ同じ物ですが、ビスケットはバターではなくショートニングを使用することが多いのが特徴です。
アメリカでスコーンと言えば、レーズンなどのドライフルーツやチョコレートなどが入り、生地にも砂糖が多く使われる甘いパンを指します。
玉ねぎやベーコンなとが入った塩味のパンもあります。

※アフタヌーンティーに欠かせない小さなパン
| 材料(12コ分) | 分量 |
| A | |
| 小麦粉 | 220g |
| ベーキングパウダー | 大さじ1 |
| 砂糖 | 30g |
| バター | 60g |
| B | |
| 卵 | 1コ |
| 生クリーム | 100ml |
| 打ち粉 | 適量 |
| 牛乳 | 少々 |
| クロテッドクリーム(又は生クリーム) | 適量 |
| 手作りジャム | 適量 |
作り方
- ボウルに(A)を混ぜ合わせます。
- 冷蔵庫から出したてのバターを、手でほぐすようにして1.に加えます。
- 2.に(B)を加えてさっくり合わせます。
- 3.を冷蔵庫で20分間程休ませます。
- 打ち粉をして4.を12等分し、手で平たく丸く形を作り、上に牛乳を塗ります。
- 5.をオーブンシートにのせて、160~170度のオーブンで約20分間焼きます。
- クロテッドクリーム(又は生クリーム)やジャムをつけて召し上がります。
<小麦粉の栄養素>
美容のビタミンとも言われて細胞の再生を促すビタミンB1・疲労回復に役立つビタミンB2、細胞の老化を防ぐビタミンEを豊富に含みます。
2.いちご大福
いちごの酸味を生かした大福もちの一種。
小豆あんとふんわりとした餅で、いちごを包んだ和菓子です。
いちごの酸味とあんの甘味が程よく、抹茶や緑茶、ほうじ茶などの日本茶と共にいただくと本当に美味!!
いちごが出回る冬から春にかけて食べられますが、近年は中のフルーツをいちごではなく、他のフルーツに変えたフルーツ大福が1年中楽しめます。
あんは白あんを使う地域と、小豆あんを使う地域に大別されます。
発祥には様々な説があります。
「元祖」を名乗る和菓子屋として、1912年創業の東京都新宿区「大角玉屋」のいちご豆大福、三重県津市「とらや本店」の白あんを使ったいちご大福などがあります。

※いちごの上部を見せて包むと可愛らしくなります
| 材料(8コ分) | 分量 |
| いちご | 8コ |
| 白あん(又は黒つぶあん) | 120g |
| A | |
| もち粉(粉末) | 120g |
| 砂糖 | 100g |
| 水 | 120ml |
| 片栗粉 | 適宜 |
※もち粉は粉末状のもので、スーパーなどで市販されています(白玉粉とは別のものです)。
作り方
- いちごは洗わずにヘタを切り、キッチンペーパーで拭いて白あんでいちごの下部2/3を包みます。
- ボウルに(A)を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせます。
- 2.をボウルのまま蒸し器に入れ、15~18分間蒸します。
- 3.を蒸し器から取り出し、木ベラでつやが出るまで練ります。
- 片栗粉を敷いたバットの上に4.を移し、まんべんなく片栗粉をまぶします。(この時、熱いので注意して下さい)
- 5.を8等分に包丁で切り分け、生地を丸くのばして1.の上にのせ、被せるように少しずつのばしながら包み、底の部分でつまんでとじ、形を整えます。残りも同じようにして、生地が熱いうちに手早く包みます。
※蒸し器の代わりに電子レンジを使用する場合(500Wを使用)
2.までは蒸し器の作り方と同様です。
3. 2.に軽くラップをかけ、電子レンジに4分間かけ、取り出して練り混ぜます。再び電子レンジに2分間かけて取り出します。
その後は、蒸し器の作り方5.と6.と同様にして下さい。
<いちごの栄養素>
レモンと同じくらい、ビタミンCが豊富に含まれます。
ビタミンCは肌をキレイにして血管を丈夫にし、免疫力を高めて病気にかかりにくくする働きがあります。

