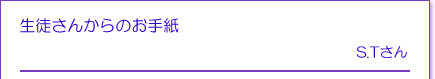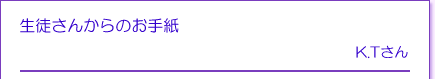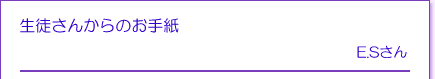今回のテーマは"夏"です。
ちぎり絵も夏を思わせるうちわや扇子に貼ることが出来ます。うちわや扇子、それぞれには凸凹があるので、貼り方、糊のつけ方には気をつけましょう。 |
 |
ピンクとブルーのお花を作ります。紙は板締和紙を使います。
板締の濃淡を使い色のうすい所がめしべになる様に使います。
花びらのちぎり方は2枚で仕上げます。
葉は緑色の4種類の板締和紙を使います。
大きな葉は濃い色、小さな葉は新芽ですので薄い色が良いでしょう。
つるは草色の雲竜紙を使います。雲竜の繊維を抜いて下さい。
その時太いのや長いのは目打ちで半分に割って使います。 |
|
 |
人物画は先に顔や体から貼ります。髪の毛は黒の雲竜紙で貼り、頭のはえぎわは黒の雲竜紙の毛羽を利用します。
かんざしは、無地和紙の金色でも黄色でも良いと思います。
大人と子供の着物は柄の紙を使うと便利でしょう。
目・眉毛・鼻などは黒の雲竜紙で細く手際良く仕上げます。 |
|
 |
木になっているひょうたんですので青緑の板締和紙が良いでしょう。
この時、ひょうたんの丸味に注意します。
葉は2種類の板締和紙の緑色を使います。
葉は1枚で葉のかた型にちぎります。
つるは黄緑色の雲竜紙を使い繊維を抜きます。 |
|
|
|
| 扇子には男持用と女持用とがありますが、作品にはこだわる必要はありません。 |
 |
葉の上にホタルが1匹止まっています。
葉は3種類の板締和紙を使います。
大きな葉の上にホタルを作ります。
黒の胴体・赤の頭は無地の和紙を使い、足やひげは黒の雲竜紙の繊維を使います。
草は少しうすい色の緑色を使うと良いでしょう。 |
|
 |
ピンクの花の花びらは1枚でちぎります。
葉は3種類の緑色の板締和紙を使います。
つるは黄緑の雲竜和紙の繊維を抜いて使います。
葉の葉脈は白の雲竜紙が良いでしょう。 |
|
 |
水墨月に月景をしてみました。水墨用に白から黒の濃淡で染めてある、むら染和紙を使います。
遠くの山は薄い色で近くの山になるにつれ、だんだんに濃い染めの所を使います。
右側の松の木は濃い染めの所を使い、重ね貼りをします。
松の葉は濃淡をうまく利用して、遠近感をだします。この時、松の葉の貼りすぎに注意して下さい。 |
|
今回で平野滋子先生の執筆の「和紙ちぎり絵」は終了しました。
長い間のご愛読ありがとうございました。